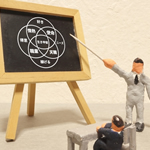空虚とは?
「なんだか満たされない」
「心にぽっかり穴が開いたみたい」
そんな「空虚」な心に悩む人が、現代人の中に増えているといいます。
「空虚」とは、文字通り「何もない状態」を表しますが、
私たちが感じる空虚感は、もっと複雑で言葉にしにくい感覚です。
現代社会は、かつてないほど便利になり、誰もが繋がり、
ある程度の自由を手に入れました。
しかしその一方で、私たちは時に強い孤独を感じ、
「何かが足りない」という満たされない感覚に襲われます。
ところが、その空虚な気持ちには重大な意味があります。
今回は、この捉えにくい「空虚」という感情について
深く掘り下げ、その解決策を解説します。
空虚とは
「空虚」は、私たちの心や存在の状態を表します。
辞書にはこう出ています。
くうきょ【空虚】
●そこを満たしているべきものが何も無い様子。
●見せかけの形だけで実質的な価値・内容が無い様子。(引用:『新明解国語辞典』第八版)
このように、物理的に何もない状態や、内容が伴わない見かけだけのものを指すのが「空虚」の基本的な意味です。
しかし、私たちが心に「空虚さ」を感じる時、
それは「人生に何も満たされていないような感覚」や
「心にぽっかりと穴が開いたような寂しさ」として現れます。
喜びや悲しみといった感情が薄れ、何をやっても満たされない、
そんな寂しさや無意味感が、空虚感です。
空虚な感情になると、人はどうなってしまうのでしょうか。
空虚な人になるのは危険?
「空虚な人」とは、心に充実感や生きがいを感じられず、
まるで空っぽのような感覚を抱えている人を指します。
そんな空虚な状態が続くと、マイナスな言動を引き起こしてしまう可能性があります。
例えば、ドイツの文豪ゲーテは、このように言っています。
 ゲーテ
ゲーテ最も空虚な人は(他人に対して)我を張りすぎる
(ゲーテ)
自分の中に確固たるものがないため、自信がなく、
それを隠すために虚勢を張ってしまうのです。
深刻な場合には、自分が生きている実感を得るために、
他人に何かを強要したり、相手の時間を必要以上に奪ったりする行動に出ることもあります。
また、空虚な人は、人間的な魅力に欠けるともいわれます。
物事に対して喜びを感じられず、明るいエネルギーを発していないため、
周囲の人々も近寄りがたく感じてしまうのかもしれません。
さらにひどいケースでは、他人の喜んでいる姿を馬鹿にしたり、見下したりすることさえあります。
自分の内側の空虚さを埋められない苛立ちが、他人への攻撃的な態度につながってしまうのでしょう。
中には、他人ではなく、自分の喜びに対して罪悪感を覚える人もいるようです。
そして空虚な人は、たとえお金や財産に恵まれたとしても、
常に退屈な心に苦しみます。
人生で本当に何をなすべきか、何が自分にとって大切なのかが分からず、
表面的な豊かさだけでは心の空洞を埋められないのです。
では「空虚ではない人」はどんな人なのでしょうか?
「空虚」には対義語があります。
「空虚」の反対と比べれば「空虚な人」が、より鮮明になります。
空虚の反対は充実
空虚の対義語として「充実」が挙げられます。
「空虚」の反対は「充実」です。
物理的な充実であれば、必要な物や人が十分に揃っている、中身が満杯という意味になります。
一方、心の充実は、目標を達成したり、良好な人間関係を築いたりすることで得られる感覚です。
心が充実感で満たされている人は、他人に対して必要以上に自己主張したり、他人の喜びを蔑んだり、人生がつまらないと嘆いたりすることはありません。
空虚感を克服することは、充実した人生を送る上で非常に重要な鍵となるのです。
この空虚な心の原因は何なのでしょうか?
空虚な心について、心理学の分野では「実存的空虚」とも言われます。
実存的空虚とは
何をしても心にぽっかりと穴が開いたような、人生に意味を感じられない空虚感を
「実存的空虚」と言います。
ロゴセラピーという心理療法を広めた、ジョセフ・B・ファブリィは、
「実存的空虚」は、老若男女、お金持ちの人、貧しい人などに関係なく持っているといいます。
この実存的空虚は、私たちの体や心に影響を与えるといわれます。
ヴィクトール・E・フランクルの心理学を分かりやすく解説した人で、ロゴセラピーを研究していたD.F.トウィディは、
「実存的空虚」は、純粋に精神病とまでは言えないものの、
しばしば、ノイローゼや不安症のような神経症的な問題の土台となりやすいと指摘しています。
なぜ、私たちはこのような空虚感を抱いてしまうのでしょうか。
最初に「実存的空虚」を提唱したのはヴィクトール・フランクルです。
フランクルは、『現代人の病』という論文集や『意味への意志』という講演集の中で、生きる意味が分からないという空虚感を「実存的空虚」と名付けています。
空虚についてフランクルの見解
ヴィクトール・E・フランクル(1905~1997年)は、第二次世界大戦中にナチスの強制収容所を生き抜いた経験を持つ心理学者です。
その壮絶な体験を綴った著書『夜と霧』は、世界中で読み継がれる名著です。
『夜と霧』の内容については、こちらの記事をご覧ください。
➾夜と霧のあらすじとフランクルが伝えたかった生きる意味
フランクルは、「ロゴセラピー」という独自の心理療法を確立し、
生きる意味を見出せない多くの人々を元気づけようとしました。
彼の心理学は、精神分析のフロイト、個人心理学のアドラーと並び、
「第三のウィーン学派」と称されています。
そのフランクルは、現代人が苦しむ空虚感を「実存的空虚」として捉え、
その原因を深く掘り下げようとしています。
空虚感を感じるタイミング
「実存的空虚」とは、人生を生きるに値するものという実存の意味、つまり人生の意味を喪失した状態をいいます。
「なんのために生きるのか分からない」
「何をやっても退屈」
「生きてる意味が分からない」
という気持ちを抱えて生きている状態です。
この実存的空虚になるタイミングは、一言でいえば
「することがない退屈しきった時」だといいます。
例えば、大学受験という明確な目標に向かって努力してきた高校生が、無事に合格した後、目標を失って空虚感を覚えることがあります。
これは、目標達成という区切りを迎えたことで、
次に取り組むべきことを見失ってしまうために起こります。
そして、新たな目標を見つけられないまま、漫然と大学生活を送ってしまう人も少なくありません。
社会人になり、仕事に就いたとしても、毎日が家と会社の往復で、自分の人生に満足できないと感じる瞬間が訪れます。
子育てを一生懸命頑張った親は、子供が成長して家を巣立った後、心に大きな穴が開いたように感じることもあります。
子供の独立は喜ばしいことですが、長年の役割を失ったことで、自分が何をすべきか分からなくなるのです。
また、特に大きな出来事がなくても、ふと自分の過去を振り返ったり、今の自分や将来について真剣に考えたりした時に、急に人生の虚しさや退屈さを感じることがあります。
なぜこのような状態になるのでしょうか。
実存的空虚に苛まれる2つの原因
なぜ多くの人が、心にぽっかりと穴が開いたような感覚を抱いたり、何をやってもつまらないと感じるのでしょうか。
フランクルは、『現代人の病』 にその原因を2つ挙げています。
1つは「本能の喪失」、もう1つは「昔ながらの教え(伝統)の喪失」です。
1つ目の「本能の喪失」というのは、本能的な命令が人間には存在しないということです。
動物には、お腹が空いたら食べる、危険を感じたら逃げる、といった生まれつき備わった行動パターン、つまり本能があります。
それに対して人間は、動物のように本能だけで生きているわけではありません。
考える力を持つ人間には、生まれた時から「これをしなさい」という明確な本能的な命令は存在しないのです。
これがフランクルが言う「本能の喪失」です。
本能を失ったことで、私たちは自らの人生に意味を見出さなければならなくなりました。
そこで、かつての社会では、親や周囲の人々から
「こう生きるのが当たり前」
「これが正しい道だ」
といった伝統的な教えが伝えられてきました。
地域の決まり、昔からの言い伝えといった「伝統」が、
何をすべきか、どう生きるべきかの指針となっていたのです。
そのため昔の人々は、生きる意味を周りの環境から与えられ、
それを信じていれば問題ありませんでした。
しかし現代社会は、多様な価値観が存在し、個人が自由に選択できることが非常に多くなっています。
その結果、「これが当たり前」という共通の価値観が薄れてきます。
これが2つ目の「伝統の喪失」です。
この伝統の喪失によって、
「何を信じて生きていけばいいのだろう?」
「何を目標にすればいいのだろう?」と迷うようになります。
自分が本当に何をしたいのか、何が大切なのか、分からなくなってしまったのです。
自分で生きる意味を見出せない時、人は生きていくための指針を
自分ではなく、他人に求め始めます。
他人の意見に従う人々
何かに生きる意味を見出さなければ、人は生きてはいけません。
自分の意見や価値観が曖昧になった時、周りの人がやっていることや、周囲の意見や考えをマネをする「追随主義」の生き方をする人が多くなります。
「あの人もやっているから自分もやる」
「あの人が言っていたから自分もそう考える」といったように、
主体性を持たずに他者の行動や意見に流されてしまうのです。
また、権力者や社会的な地位の高い人、あるいは世の中の雰囲気などによって、言われるがままに行動して「全体主義」に利用されてしまう人も増えると、
フランクルは『意味への意志』で指摘しています。
「国がやっているから間違いないだろう」
「みんなが言っているから悪いことはないだろう」といった
思考停止の状態に陥ってしまうのです。
しかし、このような生き方では、結局のところ他者の意見に振り回されているだけで、本当に自分の人生を生きているとは言えません。
そのため、心の奥底では
「自分の人生って、一体何なんだろう。意味なんてないのかな?」
という疑問や空虚感が拭えないのです。
では、フランクルはどのようにして自分の人生に意味を見出そうとしたのでしょうか。
フランクルの空虚感への対処法
フランクルは『医師による魂の配慮』の中で、人間が主体的に人生の意味を見出すのではなく、「人間は、人生から問いかけられている存在」だと捉えました。
つまり、私たちが「本当は何をしたいか」「何を望んでいるか」と悩む時、
「私はどうしたいか」という自己中心的な視点から離れ、
人生の悩みを「人生からの問いかけ」として捉え直すことを提案します。
具体的には、
「人生は私に何を求めているのか」
「何を問いかけているのか」
「私の使命は何なのか」
と考えることで、より広い視野で自分の人生を見つめ直し、新たな視点を得られるというのです。
また、辛い出来事に遭遇した際に、「人生に何の意味があるのか」と問い詰めるのではなく、「この出来事にはどんな意味があるのか」と人生からの問いかけとして捉え直すことで、新たな気づきや意味を見出すことを勧めています。
ですが、このやり方には大きな弱点があります。
生きがいと真の生きる意味の違い
フランクルが提唱する空虚感への対応には、大きな弱点があります。
それは、彼の方法によって見つかるのは、あくまで一時的な「生きがい」に過ぎないという点です。
生きがいとは、一時的には私たちを安心させたり、満足させたりするかもしれませんが、
それは時間とともに色あせてしまう、一時的な幸せに過ぎません。
とても寂しい時、「私の人生が結婚相手を見つけなさい、と言っている」と考えれば、少し元気が出て婚活を頑張れるかもしれません。
また、とても退屈な時、「私の人生が新しい趣味を見つけなさい、と言っている」と考えれば、部屋を出てロッククライミングなど、これまでやったことのない行動を起こせるかもしれません。
もしペットが亡くなって呆然としている時なら、「私の人生が新しい家族を迎えなさい、と言っている」と思うことで、少し心が慰められるかもしれません。
しかし、それはしばらくの間のことです。
この方法では、私たちが生きている中で感じる、この心のぽっかりとした穴のような空虚感は、完全に埋めることはできません。
この空っぽな感じは、お金持ちになったり、偉くなったり、欲しいものを手に入れたりしている間は、ごまかせるように思えます。
ですが実際には、それらは一時的な満足感で終わり、根本的な解決にはならないのです。
生きがいについて、詳しくは次の記事をお読みください。
➾生きがいない・生きがいが欲しい人へ生きがいの意味を解説
ですが実は、空虚感を解決する答えが、仏教にはあります。
生きる目的のない人生
生きる意味が分からず、空虚感を抱えたまま、
ただ生きているだけの人生がどのようなものなのか、
中国の高僧、曇鸞大師は、尺取り虫のたとえを用いて教えられます。
そして、人生に本当の生きる意味を与えるために、仏教があることを教えられています。
曇鸞大師の著書『浄土論註』には、次のようにあります。
三界を見そなわすに、これ虚偽の相、これ輪転の相、これ無窮の相にして、蚇蠖の循環するが如く、蚕繭の自縛するが如し。
(漢文:見三界 是虚偽相 是輪転相 是無窮相 如蚇蠖循環 如蚕繭自縛)(引用:曇鸞大師『浄土論註』)
「三界を見そなわすに」とは、「三界」は私たちが生きている世界です。
仏様が、私たちが生きている世界をご覧になると、という意味です。
「これ虚偽の相」とは、求めているものはすべて嘘偽りのものばかりで真実がなく、真の生きる意味といえるものがない、ということです。
「これ輪転の相、これ無窮の相」とは、車の輪がぐるぐる回るように、果てしなく遠い過去からゴールのない円形トラックを走り続けている、これはどこまでいっても永遠に極まることがない、際限がない、ということです。
だからゴールを突破したという心からの喜びがない人生になります。
これを「流転輪廻」ともいわれます。
流転輪廻も、車の輪が同じところをぐるぐる回るように、毎日が同じことの繰り返しで、人が生きる意味が分からず、果てしなく苦しみ続けることになります。
それを「蚇蠖の循環するが如く」とたとえられています。
「蚇蠖」とは、尺取り虫のことです。
尺取り虫は、丸い植木鉢のふちに置くと、体を曲げたり伸ばしたりしながら、植木鉢のふちを死ぬまでぐるぐる歩き続けます。
尺取り虫自身は、小さくて先のほうまで見えないので、まっすぐ進んでいるつもりだと思いますが、人間が見ると、実際は同じところをぐるぐる回っているだけだと分かります。
人間も、進歩向上しているつもりですが、仏様からご覧になると、実際には同じところをぐるぐる回って死んでいくだけです。
その終わりなく繰り返される輪廻のすがたを、尺取り虫が進む姿にたとえて教えられています。
「蚕繭の自縛するが如し」とは、蚕が自分の吐き出した糸で体を縛り、自由をなくし、最後、熱湯で茹でられるように、
流転輪廻は、自業自得であることを意味しています。
このような人間を救うために、仏教では本当の生きる意味を教えられているのです。
私たちが抱く空虚感は、仏教で教えられる本当の生きる意味を知ることでなくなり、
それによって充実した人生を送れる自分になります。
では、仏教ではどのように生きる意味を教えられているのでしょうか。
仏教に説かれる本当の生きる意味とは
今回は空虚の意味について、詳しく解説しました。
私たちの心の空虚とは、生きる意味が分からない心であり、何をしても退屈な心です。
この空虚感を感じたままだと、人は自分の幸せを見出せないだけでなく、
他人に対しても横柄な態度をとったりして、魅力的な人に見られません。
空虚感の原因を解決し、充実した人生にする必要があります。
その空虚について、オーストリアの精神医学者、ヴィクトール・フランクルは「実存的空虚」として分析し、解決策を示しました。
しかし、フランクルの示す解決策は、一時的な生きがいは見つかっても、それはやがて色あせてしまうので、本当の生きる意味と言えるものはありません。
本当の生きる意味は、仏教にしか教えられていないのです。
その本当の生きる意味とは何かということについては、仏教の真髄ですので、
以下の電子書籍とメール講座にまとめておきました。
ぜひ一度見てみてください。
関連記事
この記事を書いた人

長南瑞生(日本仏教学院創設者・学院長)
東京大学教養学部で量子統計力学を学び、1999年に卒業後、学士入学して東大文学部インド哲学仏教学研究室に学ぶ。
25年間にわたる仏教教育実践を通じて現代人に分かりやすい仏教伝道方法を確立。2011年に日本仏教学院を創設し、仏教史上初のインターネット通信講座システムを開発。4,000人以上の受講者を指導。2015年、日本仏教アソシエーション株式会社を設立し、代表取締役に就任。2025年には南伝大蔵経無料公開プロジェクト主導。従来不可能だった技術革新を仏教界に導入したデジタル仏教教育のパイオニア。プロフィールの詳細・お問い合わせ
X(ツイッター)(@M_Osanami)、ユーチューブ(長南瑞生公式チャンネル)で情報発信中。メールマガジンはこちらから講読可能。
著作
- 生きる意味109:5万部のベストセラー
- 不安が消えるたったひとつの方法(KADOKAWA出版)
京都大学名誉教授・高知大学名誉教授の著作で引用、曹洞宗僧侶の著作でも言及。