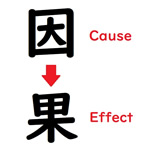智慧とは?
智慧は「ちえ」と読みます。
仏教は智慧の宗教ともいわれますが、仏教でいわれる智慧は、世間でいう知恵と本質的に異なり、はるかにもの凄い働きがあります。
智慧とは一体どんな意味で、どのように実践すればいいのでしょうか?
仏教は智慧と慈悲の教えですので、慈悲との違いも分かりやすく解説します。
仏教以外の智慧の意味
知恵という言葉は、仏教以外でもよく使われます。
代表的なものとしては、世間的な知恵と、西洋哲学でいわれる知恵の2つがあります。
それぞれどんな意味なのでしょうか。
1.世間的な知恵
同じ「ちえ」と言っても、世間的な「知恵」の場合、漢字が簡単です。
この知恵は、知識よりは一段ハイレベルな意味で、
どれだけ知識が豊富でも、知恵がないと知識を正しく使うことができません。
ですから、知識が豊富というのは単に情報量が多いという意味ですが、
知恵は、頭の良さや判断力という意味で使われます。
知恵のある人というと、頭のいい人や、機転の利く人のことをいいます。
辞書にはこのように書かれています。
①生まれつき備わった頭脳の働きとしてとっさの判断や的確な処理ができる能力。
(引用:『新明解国語事典』第八版)
中国の思想家である老子は、「知恵出でて大偽あり」といい、
人間に知恵が備わったことで大きな偽りが起き、世の中が乱れたと嘆きました。
キリスト教では、アダムとイブは「知恵の実」を食べたことで、裸であることの恥を覚えたといいます。
このような知恵も世間的な意味での知恵にあたります。
2.哲学でいう知恵
哲学の原語は、フィロソフィーですが、
フィロソフィーは、「フィロス(愛)」+「ソフィア(知)」
という言葉ですので、
哲学にとって知恵は非常に大切です。
アリストテレスは、
知恵とは「根本原因、第一原理についての普遍的な知識」
(引用:『形而上学』)
と言っており、絶対的真理についての知識をいいます。
それはどうすれば得られるのかというと、
プラトンによれば、一つの一つの知識を積み重ねて得られるのではなく、
修行などの実践によって得られるのでもなく、
数学や物理学などの客観的、普遍的知識によって可能だと
言っています。
また、ルネサンスの古典研究に始まる人文科学においても、
文献の正確な読解と、精緻な研究による知によって、
教養を深め、普遍的な真理へ到達できるという暗黙の了解がありました。
つまり西洋には、言葉や論理を重視し、正確な読書が真理へ近づく道であるという文化的な伝統があります。
ところが20世紀には、ゲーデルが不完全性定理を証明し、
数学や論理では、どんなに頑張っても
絶対的な真理は証明できないことが分かりましたから、
数学や論理によって絶対的真理を知ることはできません。
こうして哲学でいう知恵は、実質獲得不可能な、想像上の概念ということになりました。
では、仏教で智慧とはどんな意味なのでしょうか?
仏教の智慧の意味
仏教でいわれる「智慧」は、読書やそれによる知識を重視する西洋的な知恵と違って、
実践や体験と深く結びついています。
参考までに辞書を見てみましょう。
(長いですし、読み飛ばして頂いても大丈夫です)
智慧
ちえ
一切の現象や現象の背後にある道理を見きわめる心作用。【智慧・智・慧】
第1の意味では、無常・苦・無我、縁起、中道などの諸法の道理を洞察する強靭な認識の力を指し、三学の一つとされた。
この用語としては、大乗仏教の代表的実践体系である<六波羅蜜>の最後に位置づけられ、それ以前の五波羅蜜を基礎づける根拠として最も重要なものとみなされている。第2は、<慧>(prajñā) と区別して<智>(jñāna) を用いる場合で、部派仏教以降に顕著である。
説一切有部では、慧は諸法を識別する普遍的な心作用(心所)の一つに位置づけられた。
智は心作用としては慧に含まれるが、とくに悟りにみちびく心的能力として、慧の中心的な意味を担う。
同派は、智を<有漏智><無漏智>の二智や<十智>などに分類し、下は<世俗智>から上は<無生智>(もはや再生しないと自覚する智)に至るまでの智を詳論した。
大乗仏教では、般若経およびそこに説かれた六波羅蜜の徳目の中では、とくに慧(般若)が重んじられたが、声聞・独覚、菩薩、仏それぞれの智として<一切智><道種智><一切種智>の三智なども説かれる。
一方、十地経の十地説に対応させた十波羅蜜(六波羅蜜+方便・願・力・智の四波羅蜜)の体系では、智を最高位に置く。
慧に対する智の重視はとくに瑜伽行派の実践論に顕著である。
同派は伝統的に真如を獲得させる<正智>(samyag-jñāna) を重んじ、<如理智><如量智>、あるいはまた<無分別智>(nirvikalpa-jñāna)・<後得智>の二智や、<転識得智>(識を転じて智を得ること)による四智を説くなど、<智>に関する理論を積極的に展開した。
なお、後代の密教では、真如に相当する清浄法界そのものを大日如来の法身と見なし、これに<法界体性智>の名を与えたうえで、五智・五仏の説を主張した。
また後代、とくに中国・日本仏教では<智>(知り分けるはたらき)と<慧>(知がするどく、さといこと)それぞれの語意にも関係して、智は差別・相対の世俗諦を知り分け、慧は一切の事物が平等である第一義諦(真諦)をさとるもの、とも意味づけられた。第3の意味としては、以上に示した種々な意味合いが、<智慧>という一語に込められて広い意味で用いられていると考えられる。
この場合には、多く、世俗的なさかしらな識別に対して、世事を離れた、あるいは世事を見通す叡智、かしこさを指して用いられる。(引用:『岩波仏教辞典』第三版)
ここにも最初のほうに、実践項目である六波羅蜜などが出てきています。
たくさん書いてあることで、智慧が仏教でとても重要なことは分かりますが、
少し難しく、どの内容も短い言葉で簡潔にまとめられていますので、
ここでは仏教辞典に書いていないところまで、分かりやすく解説します。
智慧とは
仏教でいわれる「智慧」は、 悟りを得させる働きのことです。
「智」も「慧」も同じ意味で、
真理をハッキリ知る働きでもあります。
これは、仏のさとりの働き、仏の力で
迷いを破る働きがあります。
また、仏のさとりによって得られる働きのこともいいます。
これを仏智といいます。
悟りというのは、下から上まで全部で52あります。
その最高のさとりが仏のさとりです。
さとりは1段違えば、人間と虫けらほど境涯が違うといわれ、
それが52段も離れているのが仏のさとりですので、
仏教の智慧は、世間の知恵とは全く違います。
仏教の「智慧」は、世間でいわれる「知恵」よりも、
画数が多くて難しい漢字が使われますのも、そのためかもしれません。
世間の知恵は想像できますが、
仏の智慧は、悟りを開かなければ想像もできない働きです。
釈迦が悟る時生じた智慧
そもそも仏教を説かれたお釈迦様が仏のさとりを開かれた時も、
智を生じ、慧を生じて、さとりを開いたといわれています。
菩薩はかく思惟する時、智生じ、眼生じ、覚を生じ、
明を生じ、通を生じ、慧を生じ、証を生ず、
菩薩は逆順に十二因縁を観じて実の如く知り、
実の如く見おわりて即ち阿耨多羅三貎三菩提を成ず。
(漢文:菩薩思惟 苦陰滅時 生智 生眼 生覚 生明 生通 生慧 生證 爾時菩薩 逆順觀十二因縁 如実知 如実見已 即於座上成阿耨多羅三藐三菩提)(引用:『長阿含経』)
「菩薩」とはお釈迦様のことです。
十二因縁とは、苦しみの12の原因のことです。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
➾十二因縁(十二縁起)とは?その意味を分かりやすく解説
お釈迦様は苦しみの原因を12回さかのぼってみられ、
その後、逆にそれらの原因がなくなったらどうなるかを見られて、
智慧を生じ、仏のさとりを開かれた、と説かれています。
ここで「明を生じた」といわれている「明」も智慧と同じ意味です。
このように、智慧とは悟りを得させる働きなのです。
智慧は仏を生む母
『大品般若経』には、智慧についてこのように説かれています。
この深般若波羅蜜はよく諸仏を生じ、よく諸仏に一切智を与う。
(漢文:是深般若波羅蜜 能生諸仏 能与諸仏一切智)(引用:『大品般若経』)
「般若波羅蜜」とは、完全な智慧のことです。
完全な智慧が仏を生み、仏に一切智を与えると教えられています。
それで、智慧は諸仏の母とか「仏母」といわれます。
智慧が仏を生むからです。
智慧は悟りを得させる働きなのです。
龍樹菩薩の解説
八宗の祖師といわれて、あらゆる仏教の宗派で尊敬されている龍樹菩薩は、
『大智度論』に、このように教えられています。
決定して知り、疑うところなきが故に名づけて智となす。
(漢文:決定知無所疑故名為智)(引用:龍樹菩薩『大智度論』)
真理をハッキリと知らせ、迷いを破るということです。
智慧によって悟りが開ける理由
では、なぜ智慧によって、悟りが開けるのかというと、
苦しみの原因を明らかにされた十二因縁で、最も深い苦しみの原因といわれるのが「無明」です。
「無明」というのは、煩悩の一つですが、
智慧がない状態のことで、無知ともいわれます。
その智慧がない状態を、智慧で滅することによって、悟りが開けるのです。
ですから、数ある煩悩の中でも根本にあるのは「愚痴」といわれますが、
これも別名を「無知」といわれます。
真理が分からない心で、十二因縁の「無明」と同じ心です。
この根本的な無知を、智慧によって破り、悟りが得られるのです。
仏教で明らかにされた苦しみの原因は煩悩ですが、
煩悩とは、悟りを妨げているものです。
その色々な煩悩の中でも、一番根本にあるのが無知であるために、
智慧によって無知を破り、悟りが得られる、ということです。
悟りを開いて得られる智慧
悟りを得させる働きが智慧ですが、
悟りを開いて得られる智慧もあります。
仏の智慧とは
煩悩の汚れのない正しい智慧によって、仏のさとりを得て働く智慧を無分別智といいます。
これは、大宇宙の真理を体得した智慧です。
仏教でいわれる真理は「真如」といわれますが、
それは、言葉を離れたものですし、想像も超えた不可思議のものです。
無分別智というと、よく主観と客観の対立を離れた智慧などと説明されますが、
真如を悟った智慧ですので、悟る智慧と悟られる真如が一体平等となっている、という意味です。
それが分別を離れているということで、無分別智と名付けられています。
有名な『般若心経』をはじめ、『般若経』といわれる様々なお経がありますが、
「般若」とは智慧のことなので、
『般若経』というのは、仏の智慧を説かれたお経です。
その内容は、主に「空」について説かれています。
お釈迦様が悟りを開かれた時も、縁起を観察して仏のさとりを開かれましたが、
「空」というのは、縁起と同じです。
縁起というのは、因果の道理と同じことで、
簡単にいえば「すべての結果には必ず原因がある」ということですが、
それが智慧と深い関係にあるのです。
空について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
➾龍樹菩薩(ナーガールジュナ)の大乗仏教と空とは?
悟りを開いた後に得られる智慧
そして、仏のさとりを開いた後でも、人々を幸せに導くためには、分別のある智慧も必要です。
ですから、仏様には、無分別智以外に、有分別智もあります。
特に、仏のさとりを開いた後に得られる有分別智を後得智といわれます。
後得智で有名なのは、神通力も、後得智の一種です。
神通力の一つの漏尽通は、煩悩が尽きて輪廻を離れたことを自覚する智慧ですので
「漏尽智」ともいわれます。
また、仏様にしか備わっていない功徳を「十八不共仏法」といいますが、
その十八の中の十をしめる十力は、すべて智慧の力です。
仏様は、智慧の方なのです。
そして、仏さまの智慧をよく光明といわれます。
仏様はよく後光が差しているイメージがありますが、
あれが仏の光明です。
仏が放たれている光明というのは、智慧の働きのことです。
仏さまは、すべての人を救わんと光明を放たれて、
苦しみ悩むすべての人を、悟りへ悟りへと引っ張っておられるのです。
ですが、仏様のお徳は智慧だけではありません。
それらの智慧は、慈悲に裏付けられた智慧なのです。
智慧と慈悲の違い
仏様は、智慧と慈悲の覚体です。
覚体とは、さとられ体得された方ということで、
智慧と慈悲を兼ね備えられた方が仏様ということです。
仏様は智慧を体得されているだけでなく、仏の心は大きな慈悲の心であることを、
『観無量寿経』にこう説かれています。
仏心とは大慈悲これなり。
(漢文:仏心者大慈悲是)(引用:『観無量寿経』)
智慧と慈悲の違いについて簡単に説明すると、
智慧とは、迷いを破る力であり、
慈悲は、不幸をなくして幸福を与える心、
「抜苦与楽」の心のことです。
親が子供を育てる時でも同じです。
このような歌があります。
父は打ち 母は抱いて 悲しめば
変わる心と 子や思うらん
子供が悪いことをすると、お父さんは厳しくひっぱたいたり叱ってしつけます。
子供は善悪が分かりませんから、これは大切なことです。
ですが、厳しくするだけではひねくれてしまいます。
そこで、お母さんは子供を抱いて優しく慰めます。
そうすると子供は、お父さんが嫌いでお母さんが好きになります。
ですが、二人とも優しく接して甘やかしすぎると
子供がどら息子になってしまいますし、
二人とも厳しいと、子供は自己評価が低くなったり、グレたりしてしまいます。
一人が厳しく、一人が優しいのは、子供の幸せにとって必要なことで、
どちらも子供に幸せになってもらいたいという親心なのです。
この父親の厳しさのようなものが智慧、
母親の優しさのようなものが慈悲にあたります。
仏様は、すべての人を本当の幸せに導くために、
智慧と慈悲を兼ね備えておられるのです。
ですから仏様は、大慈悲心をもって、
すべての人を救いたいと誓っておられます。
慈悲については、こちらの記事に詳しく書いています。
➾慈悲の意味をできるだけ簡単に分かりやすく解説
しかし、仏様はお慈悲な面ばかりではありません。
迷いを決して許さず、迷いを破る智慧の働きもあるので、
仏の慈悲は、智慧に裏付けられた慈悲なのです。
このように、智慧と慈悲は全く違いますが、
それでいて智慧と慈悲は深い関係があるのです。
最後に、智慧には実践もあります。
智慧の実践というのは、
一体どうすればいいのでしょうか?
智慧の実践
智慧が悟りを得させる働き、ということが分かったら、
どのように実践すればいいのでしょうか。
三学の慧学
悟りへ向かうための実践を仏教では三学といわれます。
三学というのは、戒学、定学、慧学の3つで、
戒律と禅定と智慧のことです。
この戒・定・慧の三学の智慧でいわれる智慧は、悟りへ向かって導く実践のことなので、仏の智慧だけではありません。
大きく分けて3つあります。
これを「三慧」といわれ、聞慧、思慧、修慧の3つです。
ついでに世間的な知恵である生得慧も加えると四慧となります。
まず生得慧というのは、人間が生まれつき持っている知恵のことです。
仏教を聞く前からある、世間的な知恵のことです。
次に聞慧とは、仏の教えを聴聞して起きる智慧です。
つまり、仏教を聞いて起きる智慧です。
生得慧によって仏教を聞いて、聞慧を起こします。
ですが、それは知識を得たようなもので、
それは重要ですが、そこで終わりではありません。
その次の思慧とは、仏教の教えを思うことによって得られる智慧です。
聞いたことをよく理解する必要があるようなものです。
そして最後の修慧とは、仏の教えを修めて得られる智慧です。
仏教を聞いて理解することは大切ですが、
そこで止まるのではなく、それらに基づく実践をして智慧を発するのが重要なのです。
六波羅蜜の智慧
そういうことで、私たちが実践すべき六波羅蜜の最後にも
智慧が教えられています。
智慧は、お釈迦様があらゆる善を6つにまとめられた六波羅蜜の6番目に教えられ、実践すべき重要な項目です。
六波羅蜜について、詳しくは下記をご覧ください。
➾六波羅蜜とは?内容6つと実践方法を簡単に分かりやすく解説
この六波羅蜜の最後に教えられる「智慧」というのは、
大宇宙の真理である因果の道理を明らかに見て、
人格を高めなさいということです。
これは六波羅蜜のこれまでの5つである
のまとめです。
他人に親切にしたり、言行一致させたり、
感情的にならず、心をしずめて継続的に努力していくと、
心が磨かれて、人格が高められ、輝く人になっていきます。
そうなると、世間でも、周りの人から尊敬されるようになり、
発言が受け入れられやすくなり、人間関係もスムーズになります。
世間でいう「知恵」は、頭の良さとか、判断力のことですから、
仏教でいわれる「智慧」と、いかに違うかが分かります。
この仏教の智慧を一言でいうと「修養」ということです。
英語でいえば「セルフカルティベーション(self-cultivation)」です。
六波羅蜜の前の5つを総括されたもので
「因果の道理を信じて、悪いことをやめて、善いことをしなさい」
ということです。
掃除の五徳
修養というのは、人格を磨くことですが、
その基礎として、とてもいいのが掃除です。
お釈迦様は、仏道修行の基本として掃除を勧められました。
『毘奈耶雑事』にこのように説かれています。
仏、諸の苾芻に告げたまわく、凡そ掃地は五つの勝利あり。
いかんが五と為す。
一つには自心を清浄にす。
二つには他心を浄らかにせしむ。
三つには諸天歓喜す。
四つには端正業を植。
五つには命終の後まさに天上に生ず。
(漢文:佛告諸苾芻凡掃地者有五勝利 云何爲五 一者自心清淨 二者令他心淨 三者諸天歡喜 四者植端正業 五者命終之後當生天上)(引用:『根本説一切有部毘奈耶雑事』)
お釈迦様は、たくさんの弟子たちに言われた。
地面を掃くことには、5つのすぐれた利点がある。
それは何かというと、
1つには自らの心が清らかになる
2つには、他人の心も清らかになる
3つには、神々が喜ばれる
4つには、やがて幸せになる種をまける
5つには、死んだ後に天上界に生まれられる。
これを「掃除の五徳」といわれます。
賢愚経のドンマカセン夫人
そして、お釈迦様は、お経に掃除を繰り返し説かれています。
例えば、赤塚不二夫『天才バカボン』のレレレのおじさんのモデルになったシュリハンドクにも、掃除を勧められています。
その結果シュリハンドクは、掃除三昧によって悟りを得ています。
それについて詳しくは、以下の記事をご覧ください。
➾周利槃特(チューラパンタカ)とは?レレレのおじさんの如く掃除三昧で悟りを開いた話
また、『賢愚経』にはこんな話もあります。
お釈迦様が祇園精舎におられた時、舎衛国の大臣のリキミ(梨耆弥)が、末っ子の嫁探しを始めました。
すると外国のドンマカセン(曇摩訶羨)の娘がたいそう利口者だという評判だったので、縁談がまとまりました。
ドンマカセンは実は、亡命した舎衛国の波斯匿王の弟でした。
娘を迎えるリキミの一向が到着すると宴会でもてなし、万事つつがなく手はずが整います。
いよいよ娘がお嫁に旅立つ時、賢夫人と名高いドンマカセンの夫人が、みんなの前で娘にこう言います。
「これからは、いつもいい服を着て、いつも美味しいものを食べ、毎日鏡を見るのですよ」
(常著好衣 恒食美食 日日照鏡)
リキミは内心「まじか?」と思いましたが、今更破談にすることもできず、娘を国へ連れて帰りました。
これからどうなることだろうと思いきや、お嫁さんが家に入ると、毎日朝は暗いうちから起き出して、掃除をしたり、みんなの食事を準備したり、大変な働き者です。
驚いたリキミが、旅立ちの時のお母さんの言葉について尋ねると、
娘はひざまずき、輝く笑顔でこう答えました。
「そのことでしたら、いい服を着ろというのは、いつも清潔にしなさいということです。
美味しいものを食べなさいというのは、よく働けば粗末な食事でも美味しいということです。
鏡を見なさいというのは、早起きして掃除をしなさいということです」
(教令早起 灑掃内外)
それを聞いたリキミは、ますます手厚く接したと説かれています。
(出典:『賢愚経』梨耆彌七子品第三十二)
このように、掃除をして清潔にしておくことは、とても大切です。
掃除は人間形成にもよく、すべてに通じるのです。
具体な実践例
それでは、私たちはどうすればいいのでしょうか。
例えば自分の部屋を見てみましょう。
部屋の乱れは心の乱れ、それが今の自分の心の現れです。
部屋の中以外にも、机の中や、鞄の中、車の中、
パソコンのデスクトップはどうでしょうか。
確かに、机の上がごちゃごちゃだったり、髪がボサボサ、服はシワシワで、
すごい能力の人はいます。
しかし、そんな人は人格者とは言われません。
「あの人はすごいけど、ちょっと変わってる」
と言われてしまいます。
まず、使わないものは、捨てましょう。
よく使うものを、場所を決めて整理整頓します。
一度掃除してもすぐに汚れるので、
年末大掃除だけでなく、定期的に掃除をする必要があります。
いつ誰に見られてもいいように、掃除、整理整頓をすると、
自分の心に目が向き、落ち着いてきます。
特に有効なのはトイレ掃除です。
そして、掃除や整理整頓が終わって周りが綺麗になると、
気持ちよくなり、何もかもはかどるようになります。
今すぐやってみましょう。
なぜ六波羅蜜の最後に総括されているの?
よく西洋の考え方では、
「もれなく・だぶりなく」
(MECE:Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive)
がいいとされています。
それは、何かを網羅したり、抜けを探すときに有効です。
しかし、そうでなければならないというものではありません。
お釈迦様の目的は、何かを網羅することではなく、
私たちを本当の幸せに導くことですから、
最後に総括されて、私たちを導いておられるのです。
では、どうすれば本当の幸せになれるのかというと、
迷いの根本原因を知り、それを断ち切らなければなりません。
それについては、仏教の真髄ですので、とても一言では言えないのですが、
電子書籍とメール講座にまとめておきました。
以下のページから、一度見ておいてください。
関連記事
この記事を書いた人

長南瑞生
日本仏教学院 学院長
東京大学教養学部で量子統計力学を学び、卒業後、学士入学して東大文学部インド哲学仏教学研究室に学ぶ。
仏教を学ぶほど、その底知れない深さと、本当の仏教の教えが一般に知られていないことに驚き、何とか1人でも多くの人に本物を知って頂こうと、失敗ばかり10年。たまたまインターネットの技術を導入して爆発的に伝えられるようになり、日本仏教学院を設立。科学的な知見をふまえ、執筆や講演を通して、伝統的な本物の仏教を分かりやすく伝えようと今も奮戦している。
仏教界では先駆的にインターネットに進出し、通信講座受講者4千人、メルマガ読者5万人。X(ツイッター)(@M_Osanami)、ユーチューブ(長南瑞生公式チャンネル)で情報発信中。メールマガジンはこちらから講読可能。
著作
- 生きる意味109:5万部のベストセラー
- 不安が消えるたったひとつの方法(KADOKAWA出版)