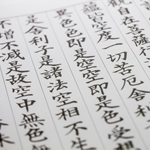般若心経とは?
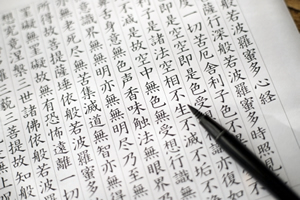
般若心経
『般若心経』は、非常に有名なお経で、「天下第一のお経」ともいわれます。
真言宗を開いた弘法大師は、「簡にして要、約にして深し」(引用:『般若心経祕鍵』)と言っています。
浄土真宗と日蓮宗以外なら、天台宗でも真言宗でも、法相宗でも禅宗でも浄土宗でもよく読まれたり、写経されます。
大変親しまれているため、あのラフカディオ・ハーンの「耳無芳一」の体に書かれた経文も『般若心経』です。
しかしその内容は初心者向けではなく、まるで仏教の教えを否定しているかのような危険な側面もありますので、誤って理解すると大変なことになります。
一体どんなお経なのでしょうか?
般若心経の本当の意味についてわかりやすく解説していきます。
般若心経の特徴
『般若心経』は詳しく言うと『般若波羅蜜多心経』です。
略して『心経』ともいわれます。
まず、タイトルの『般若波羅蜜多心経』はどんな意味かというと、「般若」とは、智慧のことです。
「波羅蜜多」の意味は「彼岸に到る」ということで、六波羅蜜の「波羅蜜」と同じ意味です。
「彼岸」とは浄土のことですから、浄土へ渡る、ということです。
浄土(極楽浄土)について詳しくは以下をご覧ください。
⇒極楽浄土への行き方(簡単なのに行く人がない)
実際、『大品般若経』30巻や『大般若波羅蜜多経』600巻の中には、大変よく似たところがあります 。
それらの膨大な般若経の核心を簡潔に説き明かされたお経であり、私たちを彼岸へ導こうとされたお経なのです。
般若心経の翻訳8種類
漢文の『般若心経』には、実は8種類の異なった翻訳が現存しています。
翻訳された時代順に並べると以下のようになります。
- 『摩訶般若波羅蜜大明呪経』鳩摩羅什訳
- 『般若波羅蜜多心経』玄奘訳
- 『仏説般若波羅蜜多心経』義浄訳
- 『普遍智藏般若波羅蜜多心経』法月訳
- 『般若波羅蜜多心経』般若・利言訳
- 『般若波羅蜜多心経』智慧輪訳
- 『聖佛母般若波羅蜜多経』施護訳
- 『般若波羅蜜多心経』法成訳
この中で、普通『般若心経』として広まっているのは、2番目の玄奘が翻訳したものです。
インドのサンスクリット語の『般若心経』には、最澄が中国から伝えた小本と、ネパールで発見された大本の2つがあります。
大本というのは、小本にはない最初と最後の部分があります。
サンスクリット語の『般若心経』(小本)について、詳しくは以下の記事をご覧ください。
⇒般若心経のサンスクリット原典と対訳(カタカナの読み方付き)
漢訳経典の1と2は小本に対応し、4から8は、大本に対応しています。
ここでは、一番一般的な玄奘訳の『般若心経』を解説していきます。
原文(漢文)と読み方
まず最初に、以下が『般若心経』の全文と読み方です。
仏説・摩訶般若波羅蜜多心経
観自在菩薩・行深般若波羅蜜多時、照見五蘊皆空、度一切苦厄。
舎利子。色不異空、空不異色、色即是空、空即是色。受・想・行・識・亦復如是。
舎利子。是諸法空相、不生不滅、不垢不浄、不増不減。
是故空中、無色、無受・想・行・識、無眼・耳・鼻・舌・身・意、無色・声・香・味・触・法。無眼界、乃至、無意識界。
無無明・亦無無明尽、乃至、無老死、亦無老死尽。
無苦・集・滅・道。無智、亦無得。
以無所得故、菩提薩埵、依般若波羅蜜多故、心無罣礙、無罣礙故、無有恐怖、遠離・一切・顛倒夢想、究竟涅槃。
三世諸仏、依般若波羅蜜多故、得阿耨多羅三藐三菩提。
故知、般若波羅蜜多、是大神呪、是大明呪、是無上呪、是無等等呪、能除一切苦、真実不虚。故説、般若波羅蜜多呪。
即説呪曰、羯諦羯諦、波羅羯諦、波羅僧羯諦、菩提薩婆訶。般若心経
玄奘の翻訳には「遠離・一切」の所の一切がなく、260字ですが、よく広まっているのは、上記のような、一切を加えた262字です。
読経の場合は漢字一つを一拍として読みます。
これを書き下すと以下のようになります。
書き下し文
観自在菩薩、深般若波羅蜜多を行じし時、五蘊皆空なりと照見して、一切の苦厄を度したまえり。
舎利子、色は空に異ならず、空は色に異ならず。
色はすなわちこれ空なり、空はこれすなわち色なり。
受想行識もまたまたかくのごとし。
舎利子、この諸法の空相は、不生にして不滅、不垢にして不浄、不増にして不減なり。
この故に、空の中には、色もなく、受想行識もなし。
眼耳鼻舌身意もなく、色声香味触法もなし。
眼界もなく、乃至、意識界もなし。
無明もなく、また無明の尽くることもなし。乃至、老死もなく、また老死の尽くることもなし。
苦集滅道もなし。
智もなく、また得もなし。無所得を以ての故に。
菩提薩埵の、般若波羅蜜多に依るが故に、心に罣礙なし。
罣礙なきが故に、恐怖あることなし。一切の顚倒夢想を遠離し究竟涅槃す。
三世諸佛も般若波羅蜜多に依るが故に、阿耨多羅三藐三菩提を得たまえり。
故に知るべし、般若波羅蜜多のこの大神呪、この大明呪、この無上呪、この無等等呪を。
よく一切の苦を除き、真実にして虚しからず。
故に般若波羅蜜多の呪を説く。
すなわち呪を説いて曰く、
羯諦羯諦 波羅羯諦 波羅僧羯諦 菩提薩婆訶
般若心経
ちなみに『般若心経』の和訳・現代語訳については以下をご覧ください。
⇒般若心経の全文と読み方、和訳・現代語訳
般若心経の本当の意味
以下では内容を詳しく解説しながら、般若心経の本当の意味に迫っていきます。
- 般若心経の説かれた場面
- 般若心経の目的
- 般若心経 心臓部分の意味
- 色即是空とは?
- 一切は生ずることも滅することもない
- この世のすべて(十八界)に実体はない
- 12の迷いの原因(十二因縁)にも実体がない
- 4つの真理(四聖諦)にも実体がない
- 智慧も所得もない
- 般若波羅蜜多の功徳
- 般若波羅蜜多のまことの言葉の素晴らしさとは?
- 結論
般若心経が説かれた場面
この『般若心経』はどんな意味なのでしょうか?
まず『般若心経』がどのような時に説かれたのかというと、そのことが『般若心経』の大本の冒頭部分に説かれています。

霊鷲山の先端
お釈迦さまは、三昧という心を一つにした状態に入っておられました。
そのとき、阿弥陀如来の慈悲を表す菩薩である観音菩薩が、般若の智慧を実践して一切は空であると見抜き、一切の苦しみから救われました。
すると、釈迦十大弟子の一人である舎利弗尊者が、
「般若の智慧を完成したいときにはどうすればいいのでしょうか」
と観音菩薩に質問します。
その時、観音菩薩が舎利弗尊者に説かれたのが、『般若心経』です。
般若心経の目的
まず最初に、「観自在菩薩、深般若波羅蜜多を行じし時、五蘊皆空なりと照見して、一切の苦厄を度したまえり」と説かれています。
まず、「観自在菩薩」とは、観音菩薩といっても同じです。
インドの言葉で説かれているお経を中国の言葉にするときの翻訳の違いです。
鳩摩羅什の翻訳では「観音菩薩」といわれますが、
玄奘の翻訳では「観自在菩薩」といわれます。
観音菩薩は、阿弥陀如来の慈悲を表す菩薩です。
「深般若波羅蜜多を行ずる」とは、般若の智慧を完成されたということですが、それは、六波羅蜜を実践されたということです。
「六波羅蜜」とは、次の6つです。
(それぞれどんな意味かは、リンク先の記事で詳しく解説してあります)
六波羅蜜の修行を実践した結果が、「五蘊皆空なりと照見して、一切の苦厄を度したまえり」ということです。
『般若心経』が目的としているのは、この冒頭に説かれているように、「一切の苦厄を度する」ことです。
つまり、一切の苦しみを救う、ということです。
そもそも仏教の目的が、すべての人の苦しみを救うことなのです。
仏教の教えについてはこちらをご覧ください。
⇒仏教の教えをわかりやすく簡単に学ぼう・仏教に説かれた2つのこと
『般若心経』もそのために説かれているのです。
これを忘れてしまうと、お経の表面的な意味を理解したとしても、要の抜けた頭だけの遊びになってしまいます。
このことをよく心に置いて、意味を理解するようにしてください。
般若心経の心臓部分の意味
この「五蘊皆空」が、『般若心経』に説かれる内容を一言で表した心臓部です。
有名な「色即是空」もこの一部分に過ぎません。
色即是空については以下に詳しく解説してあります。
⇒色即是空の恐ろしい意味を分かりやすく説明
五蘊の意味
五蘊とは、人間を構成している5つのものです。
「蘊」とは、積集ということで、集まりのことです。
その5つとは、色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊の5つです。
- 色蘊
- 受蘊
- 想蘊
- 行蘊
- 識蘊
それぞれどんな意味かというと、
「色蘊」とは、肉体や、その他の物質のことです。
「受蘊」とは、苦楽を感受する働きです。
「想蘊」とは、認識する働きです。
「行蘊」とは、意思をはじめとする、受蘊、想蘊以外の心の働きすべてです。
「識蘊」とは、心のことです。
このように、色蘊は肉体や世界、受蘊・想蘊・行蘊は心の働き、識蘊は心のことですので、五蘊とは、心身のことです。
その五蘊は「皆空」である、というのが「五蘊皆空」です。
皆空とは┃空の思想について
「空」とはどんなことでしょうか?
それを知るには、仏教の根幹である、因果の道理を知らなければなりません。
詳しくは以下の記事でご覧ください。
途中を省略して簡単にいえば、因果の道理とは、この世のすべては、因と縁がそろって生じている、ということです。
これをお釈迦さまは、こう説かれています。
一切法は因縁生なり。
(『大乗入楞伽経』)
「一切法」とは万物のことです。
因縁生とは、因と縁がそろって生じている、ということです。
「因」とは直接的な原因で、
「縁」とは間接的な原因のことです。
例えば、米という結果を得るためには、因はモミダネです。
ところが、モミダネを机の上に置いていても、米にはなりません。
他にも、水や土、温度、栄養など、色々なものが必要です。
これらを縁といいます。
因だけでも結果は起きませんし、縁だけでも結果は起きません。
すべてのものは、因と縁が結合して生じている、ということです。
したがって、一切に固有の実体はありません。
これを分かり易く教えたのがこの歌です。
引き寄せて 結べば柴の庵にて
解くれば 元の野原なりけり
(慈円作)
「庵」とは、テントのようなものです。
野原で草を引き寄せて、上の部分を縛ると、簡単な庵を作ることができます。
ところが、その庵には、固有の実体はありません。
草という因と縛られたという縁がそろって、一時的に庵になっているだけで、上の部分がほどかれると庵はなくなります。しかし、無になるのではありません。元の野原になります。
これは、どんなものでも同じです。
例えばパソコンにも固有の実体はありません。
色々な部品が組み立てられて、一時的にパソコンになっていますが、分解すると、パソコンはなくなります。しかし無になるのではありません。ディスプレイやキーボード、演算処理装置、記憶媒体などの部品になります。
それらの部品も、一時的にディスプレイやキーボードなだけで、分解すると、ディスプレイもキーボードもなくなります。しかし無になるのではなく、別の何かになります。
現代物理学では、そうやって分解していった一番小さい要素は、素粒子になります。
素粒子には大きさはありません。ではなぜこの世に大きさがあるのかというと、大きさのない素粒子の相互関係によって、大きさのある世界ができています。
つまり、物理学でもこの世に実体はないのです。
従って、五蘊にも実体はありません。
私たちの心にも体にも、実体はないのです。
これは仏教の根幹である因果の道理から必然的に出てくることです。
観音菩薩は因果の道理にしたがって六波羅蜜を実践し、五蘊皆空と知らされ、一切の苦しみの解決を体験されたのです。
色即是空とは?
次に、有名な「色即是空」が出てくるところです。
ここで「五蘊皆空」を、このように詳しく説明しています。
「舎利子、色は空に異ならず、空は色に異ならず。
色はすなわちこれ空なり、空はこれすなわち色なり。
受想行識もまたまたかくのごとし」
舎利子の意味
「舎利子」とは、釈迦十大弟子の一人、智慧第一の舎利弗尊者のことです。
観音菩薩が、舎利弗から質問を受けたので、呼びかけられたのです。
色の意味
「色」とは、色蘊のことで、物質的なものです。
色不異空の意味
「色は空に異ならず」というのは、物質的なものに実体はないということです。
では何も無いのかというと、そうではありません。
空不異色の意味
次に「空は色に異ならず」といわれています。
因縁によって物質的なものが生じているということです。
このことを言葉を変えて、「色はすなわちこれ空なり、空はこれすなわち色なり」と説かれています。
空即是色の意味
「色即是空、空即是色」については、
色がすなわち空だというのは分かっても、
空がすなわち色だということについて疑問に感じる人があります。
なぜかというと、五蘊の中で、色以外の受想行識も空だからです。
これについては、サンスクリット語の『般若心経』をみると、こうあります。
「色は空性であり、空性こそ色である。
色から離れて空性はなく、空性から離れて色はない。
色なるものは空性であり、空性なるもの色である」
この三文を、漢訳では、
「色は空に異ならず、空は色に異ならず。
色はすなわちこれ空なり、空はこれすなわち色なり」
の二文に要約してあります。
「空はこれすなわち色なり」は、
「空性なるもの色である」に対応しており、
これは「空という性質を持つものが色である」という意味ですので、
漢訳の「空はこれすなわち色なり」もそのような意味です。
つまり色即是空イコール空即是色です。
受想行識亦復如是の意味
「受想行識もまたまたかくのごとし」とは、色蘊以外の、受蘊も想蘊も行蘊も識蘊も同じことである、ということです。
例えば受蘊でいえば、
「受は空に異ならず、空は受に異ならず。
受はすなわちこれ空なり、空はこれすなわち受なり」
ということです。
識蘊でいえば、
「識は空に異ならず、空は識に異ならず。
識はすなわちこれ空なり、空はこれすなわち識なり」
ということです。
一切は生ずることも滅することもない
次に、この五蘊皆空を別の側面からこのように教えられています。
「舎利子、この諸法の空相は、不生にして不滅、不垢にして不浄、不増にして不減なり」
諸法の意味
「諸法」とは、万物のことで、五蘊と同じです。
万物の空である姿は、生ずることも滅することもないというのは、因縁が結合したり離れたりするだけで、無から有が生じたり、有ったものが無くなったりしているわけではない、ということです。
不垢不浄の意味
「不垢にして不浄」とは、汚いとかきよらかということも因縁によるもので、汚い実体とかきよらかな実体はないということです。
例えば、唾液は、吐き出すとみんな汚いと思いますが、口の中にあるときは、殺菌作用で口の中をきれいにするものです。
誰もが汚いと思う排泄物も、体内にあるときは、食べ物だったり、腸内環境をよくする善玉菌だったりします。
体の外に出た途端、みんな汚いと思います。
このように、すべては因縁によって生じているのであって、汚いとかきよらかな実体というものもないのです。
不増不減の意味
「不増にして不減」というのも、「不生にして不滅」と同じように、すべては因縁がくっついたり離れたりしているだけで、何かが増えたり減ったりしているのではない、ということです。
その結果、どうなるのでしょうか?
この世のすべて(十八界)に実体はない
次に、このように説かれています。
「この故に、空の中には、色もなく、受想行識もなし。
眼耳鼻舌身意もなく、色声香味触法もなし。
眼界もなく、乃至、意識界もなし」
是故空中無色無受想行識の意味
まず、「この故に、空の中には、色もなく、受想行識もなし」は、五蘊皆空を繰り返されています。
「空の中には」とは、すべては因縁によって生じているのだから、ということです。
「色もなく」とは、今あると思っている物質(色蘊)も、因縁が離れたら別のものになるので、なくなってしまう、ということです。
「受想行識もなし」とは、今あると思っている苦楽の感覚(受蘊)も、イメージ(想蘊)も、意思(行蘊)も、心(識蘊)も、因縁が離れたら別のものになるので、なくなってしまう、ということです。
この世のすべてに実体はないのです。
無眼耳鼻舌身意無色声香味触法無眼界乃至無意識界の意味
次の「眼耳鼻舌身意もなく、色声香味触法もなし。眼界もなく、乃至、意識界もなし」も、この世のすべてに実体はないということを、少し別の角度からさらに詳しく説かれたものです。
一言でいうと、認識の働きも、認識の対象も、認識の主体も、実体がないということです。
まず「眼耳鼻舌身意」とは、認識する働きである六根のことです。
六根とは次の6つです。
- 眼根
- 耳根
- 鼻根
- 舌根
- 身根
- 意根
「眼耳鼻舌身意もなく」とは、これらの認識する働きも、たまたま因縁がそろって存在しているだけで、因縁が離れるとなくなる、ということです。
たとえば、視神経が損傷して目が見えなくなったり、聴覚神経がやられて耳が聞こえなくなったりします。
認識の働きにも実体はないということです。
次に、「色声香味触法」とは、六根が認識する対象の六境のことです。
六境とは次の6つです。
- 色境
- 声境
- 香境
- 味境
- 触境
- 法境
「色声香味触法もなし」とは、これらの六境も、たまたま因縁がそろって存在しているだけで、因縁が離れるとなくなります。
目に見えるものも、耳に聞こえるものも、実体はないことを「色声香味触法もなし」といわれているのです。
次に、「眼界もなく、乃至、意識界もなし」の眼界とか意識界とは、六根と六境に、認識する主体である、六識を加えたものです。
六識とは次の6つです。
- 眼識
- 耳識
- 鼻識
- 舌識
- 身識
- 意識
根によって境を認識するのは識です。
例えば現根によって色境を認識するのが眼識です。
ですから六根、六境、六識の18は、以下のように対応しています。
眼根 ─ 色境 ─ 眼識
耳根 ─ 声境 ─ 耳識
鼻根 ─ 香境 ─ 鼻識
舌根 ─ 味境 ─ 舌識
身根 ─ 触境 ─ 身識
意根 ─ 法境 ─ 意識
これらの根と境を界に置き換え、六識の後に界をつけて、18の最後を「界」としたものを「十八界」といわれます。
- 眼界 ─ 色界 ─ 眼識界
- 耳界 ─ 声界 ─ 耳識界
- 鼻界 ─ 香界 ─ 鼻識界
- 舌界 ─ 味界 ─ 舌識界
- 身界 ─ 触界 ─ 身識界
- 意界 ─ 法界 ─ 意識界
これらの十八界すべてに実体はないことを「眼界もなく、乃至、意識界もなし」といわれています。
六根にも六境にも実体はありませんが、それらを認識する6つの心も、たまたま因縁がそろって存在しているだけで、因縁が離れるとなくなります。
例えば目が見えなくなれば眼識はなくなりますし、耳が聞こえなくなれば耳識はなくなります。
死ぬと、これらの心はすべて滅びます。
このように、「眼界もなく、乃至、意識界もなし」とは、これらの十八界すべてに実体がない、ということです。
12の迷いの原因(十二因縁)にも実体がない
次に「無明もなく、また無明の尽くることもなし。乃至、老死もなく、また老死の尽くることもなし」といわれています。
「無明」とか「老死」とは「十二因縁」のことです。
十二因縁とは、私たちの12の迷いの原因を教えられたものです。
お釈迦さまは、この十二因縁を発見され、さとりを開かれた、と説かれています。
その十二因縁とは、1無明・2行・3識・4名色・5六処・6触・7受・8愛・9取・10有・11生・12老死のことです。
- 無明
- 行
- 識
- 名色
- 六処
- 触
- 受
- 愛
- 取
- 有
- 生
- 老死
十二因縁については、詳しくは以下の記事をご覧ください。
⇒十二因縁(十二縁起)私たちの12の迷いの元
この一番最初の「無明」と最後の「老死」を挙げて、途中を「乃至」で省略して、十二因縁を表しているのです。
「無明もなく、老死もない」というのは、これらの「十二因縁」に実体がないということです。
すでに五蘊皆空と説かれ、識にも受にも想にも行にも色にも、この世のすべてに実体がないことを明らかにされましたので、十二因縁にも実体はありません。
十二因縁に実体がない以上、十二因縁が尽きるということにも実体がありません。
そのことを「無明もなく、また無明の尽くることもなし。乃至、老死もなく、また老死の尽くることもなし」と説かれているのです。
4つの真理(四聖諦)にも実体がない
次に「苦集滅道もなし」と説かれています。
苦集滅道の意味
「苦集滅道」とは、四聖諦のことです。
「諦」とは真理のことで、四聖諦とは、次の4つの聖なる真理のことです。
- 苦諦
- 集諦
- 滅諦
- 道諦
それぞれどんな意味かというと、
「苦諦」とは「人生は苦なり」という真理、
「集諦」とは苦しみの原因を明かした真理、
「滅諦」とは真の幸福を明かした真理、
「道諦」とは真の幸福になる道を明かした真理、
ということです。
四聖諦についてもっと詳しくは、以下の記事をご覧ください。
これらを略して「苦集滅道」といいます。
「苦集滅道もなし」とは、これら四聖諦にも実体はない、ということです。
智慧も所得もない
次に「智もなく、また得もなし。無所得を以ての故に」と説かれています。
「智」とは智慧のことです。『般若心経』の「般若」は、智慧のことですから、ここまで説かれてきた、十八界も十二因縁も四聖諦も実体がないという五蘊皆空が智慧だろうと思います。
ところが智慧は、六波羅蜜を行じて体得するものであり、修行もせずに頭だけで考えてイメージするようなものではありません。
知る私が空なのです。
それで「智もなく」と否定されているのです。
智慧ばかりではありません。
無得以所得故の意味
次の「得もなし、無所得を以ての故に」とは、五蘊皆空ですから、何かを知ったり得たりする私も空なら、得る対象も空なので、得るということもない、ということです。
六波羅蜜を実践して高い悟りを開くと、無所得の境地に至るのです。
般若波羅蜜多の功徳・効果
次に「菩提薩埵の、般若波羅蜜多に依るが故に、心に罣礙なし。
罣礙なきが故に、恐怖あることなし。一切の顚倒夢想を遠離し究竟涅槃す。
三世諸佛も般若波羅蜜多に依るが故に、阿耨多羅三藐三菩提を得たまえり」
と説かれています。
菩提薩埵の意味
「菩提薩埵」とは、菩薩のことです。
菩薩についてはこちらをご覧ください。
⇒仏(如来)と菩薩と神の違い
般若波羅蜜多の意味
「般若波羅蜜多」とは、「般若」とは智慧のことで、「波羅蜜多」とは、彼岸に到ることですから、彼岸に渡る智慧です。
菩薩は六波羅蜜を行じて、彼岸に渡る智慧が完成すると、心に罣礙がなくなるということです。
罣礙の意味
罣礙とは、さわりということで、煩悩のことです。
「罣礙なきが故に、恐怖あることなし」とは、煩悩がなくなると恐怖がなくなるということです。
恐怖の中でも最大の恐怖は、死んだらどうなるかという恐怖です。
その死の不安もなくなります。
「一切の顚倒夢想を遠離し究竟涅槃す」からです。
顚倒夢想の意味
「顚倒」とは逆立ちしていることで、間違った考えです。
「夢想」も同じことで、妄想であり間違った考えです。
智慧を完成すれば、一切の間違った考えを離れて、死ぬと究極の涅槃に入ると教えられています。
次に「三世諸佛も般若波羅蜜多に依るが故に、阿耨多羅三藐三菩提を得たまえり」と説かれています。
三世の諸仏とは、過去、現在、未来の一切の仏のことです。
地球上では仏のさとりを開かれた方は、お釈迦さまただお一人ですが、大宇宙には、数え切れないほどのたくさんの仏様がおられるとお釈迦さまは説かれています。
それらの沢山の仏方を三世諸仏といわれています。
阿耨多羅三藐三菩提の意味
「阿耨多羅三藐三菩提」とは、仏のさとりのことです。
仏のさとりについては以下をお読みください。
⇒仏のさとりとは?大宇宙最高の真理
過去、現在、未来のすべての仏さまも、彼岸に渡る智慧によって、仏のさとりを開かれたのだ、ということです。
般若波羅蜜多のまことの言葉の素晴らしさとは?
最後に、般若波羅蜜多のまことの言葉を説かれています。
「故に知るべし、般若波羅蜜多の
この大神呪、
この大明呪、
この無上呪、
この無等等呪を。
よく一切の苦を除き、真実にして虚しからず」
呪の意味
まず、「呪」というのは、呪いのことではありません。
真言のことです。
真言とは、まことの言葉ということです。
私たち人間の言葉は嘘偽りばかりですが、仏の言葉には「仏語に虚妄なし」といわれるように、決して嘘はないのです。
是大神呪 是大明呪 是無上呪 是無等等呪の意味
「般若波羅蜜多のまことの言葉」を4通りにすばらしいといわれています。
「大神呪」とは、不可思議なまことの言葉
「大明呪」とは、明らかなまことの言葉
「無上呪」とは、この上ないまことの言葉
「無等等呪」とは、並ぶもののないまことの言葉
ということです。
能除一切苦 真実不虚の意味
「般若波羅蜜多」とは、彼岸に渡る智慧ということですから、次の
「よく一切の苦を除き、真実にして虚しからず」とは、観音菩薩のように六波羅蜜を実践し、彼岸に渡る智慧を完成すれば、自分の苦しみも他人の苦しみも本当に除くことができる、ということです。
般若心経の結論とは?
では、般若波羅蜜多のまことの言葉とは具体的には何でしょうか?
次にこのように説かれます。
「故に般若波羅蜜多の呪を説く。
すなわち呪を説いて曰く、
羯諦羯諦 波羅羯諦 波羅僧羯諦 菩提薩婆訶」
これは「般若波羅蜜多のまことの言葉」とは、「羯諦羯諦 波羅羯諦 波羅僧羯諦 菩提薩婆訶」である、ということです。
羯諦羯諦 波羅羯諦の意味
「羯諦」とは行くということです。
「波羅」とは、向こうへ、ということです。
般若波羅蜜のまことの言葉ですから、向こうというのは彼岸であり浄土のことです。
ですから「波羅羯諦」は彼岸へ往くことです。
僧羯諦の意味
次の「波羅僧羯諦」の「僧羯諦」は、到達するということですから、浄土へ往くということです。
「菩提薩婆訶」の「菩提」は仏のさとり、「薩婆訶」は成就ということです。
ですから、このまことの言葉の意味は、「仏道を求め、完成して、浄土へ往って仏に生まれた」ということです。
こうして観音菩薩は、舎利弗のどのように般若の智慧を完成すればいいのかという質問に答え終わったのです。
それは、五蘊皆空の因果の道理を信じて、彼岸へ向かって布施、持戒、忍辱、精進、禅定、智慧の六波羅蜜を実践しなさい、ということです。
それを聞かれたお釈迦さまは「その通りだ、そのように実践しなさい」といわれています。
これが『般若心経』の結論です。
般若心経の位置づけ
この『般若心経』で気をつけなければならないのは、「十二因縁」や「四聖諦」などの仏教の基本的な教えをあたかも否定しているかのように誤解しやすい所です。
ですから『般若心経』は、仏教を初めて学ぶ人に対して説かれたお経ではありません。
お釈迦さまは、まず『阿含経』で、因果の道理を説かれ、十二因縁や四聖諦を教えられます。
これを幼稚園のようなものだとすれば、いつまでもそこに留まっていればいいのではありません。
次にお釈迦さまは「方等経」を説かれます。
これは小学校のようなものです。
その次に説かれるのが「般若経」です。
これは中学校のようなものですが、そのエッセンスが『般若心経』なのです。
ですから、一番初歩的な『阿含経』よりは高度ですが、まだ高校、大学があります。
お釈迦さまは六波羅蜜の実践を勧めて、私たちに苦悩の根元を知らせ、断ち切られて本当の幸福になるところに導こうとされているのです。
では、ブッダが導こうとされている本当の幸せとはどんなものなのか、
どうすれば本当の幸せになれるのかについては、電子書籍とメール講座にまとめておきました。
一度見てみてください。
関連記事
この記事を書いた人

長南瑞生
日本仏教学院 学院長
東京大学教養学部卒業
大学では量子統計力学を学び、卒業後は仏道へ。仏教を学ぶほど、その底知れない深さと、本当の仏教の教えが一般に知られていないことに驚き、何とか一人でも多くの人に本物を知って頂こうと、失敗ばかり10年。インターネットの技術を導入して日本仏教学院を設立。著書2冊。科学的な知見をふまえ、執筆や講演を通して、伝統的な本物の仏教を分かりやすく伝えようと奮戦している。
仏教界では先駆的にインターネットに進出し、通信講座受講者3千人、メルマガ読者5万人。ツイッター(@M_Osanami)、ユーチューブ(長南瑞生公式チャンネル)で情報発信中。メールマガジンはこちらから講読可能。
著作
- 生きる意味109:5万部のベストセラー
- 不安が消えるたったひとつの方法(KADOKAWA出版)