四門出遊とは?
「四門出遊」は、「四門遊観」ともいわれ、後に仏のさとりを開いてブッダとなるシッダルタ太子が、出家を決意するきっかけとなったエピソードです。
「四門」は、東西南北の4つの門です。
「出遊」は、出て遊ぶと書いて、遊学することです。
シッダルタ太子が東西南北の4つの門を出た時、
どんなことに出会い、何を学ばれたのでしょうか?
四門出遊は、『長阿含経』『過去現在因果経』『仏本行集経』『太子瑞応本起経 』など、様々なお経で繰り返し説かれる重要な教えです。
また、『今昔物語』にも取り上げられ、昔から多くの人が知っているエピソードです。
四門出遊が多くの人に学ばれてきたのは、シッダルタ太子だけではなく私たちも、人生に欠かせない教えを、分かりやすいストーリーを通して学べるからです。
それによって人生の本質を知り、本当の幸せに向かう軌道に入ることができるのです。
その四門出遊を、今回は『太子瑞応本起経』の内容を通して、詳しく解説します。
シッダルタ太子の住んでいた城
四門出遊は、お釈迦様がまだ出家して高邁な悟りを求められる前のことです。
お釈迦様は、現在のネパール南部にあたるカピラ城を治めていた、釈迦族の王子として生まれました。
名前はシッダルタ太子といいます。
当時のカピラ城は、四方を城壁に囲まれた城塞都市で、その中に王族が住む宮殿があったと考えられています。
シッダルタ太子が生まれた時、お父さんの浄飯王は、当時有名だったアシダ仙人に太子の将来はどうなるだろうかと尋ねました。
するとアシダ仙人は、シッダルタ太子に三十二相が現れているのを見て、
「将来は、全世界を支配する偉大な王になるか、
あるいは無上の悟りを開いてブッダになるでしょう」
と言いました。
アシダ仙人のエピソードについて、詳しくは以下の記事をご覧ください。
➾ブッダ(お釈迦様)の生涯と教えを分かりやすく簡単に解説
浄飯王は、アシダ仙人の言葉を大変喜びます。
ぜひ偉大な王になってもらいたいと思った浄飯王は、シッダルタ太子が世の中の苦しみを知り、真の幸せを求めて出家しないよう、宮殿の中で太子を大切に育てていきます。
シッダルタ太子に与えられた宮殿は、三時殿といわれます。
三時とは、夏期、雨期、冬期のことです。
日本は春夏秋冬の四季ですが、お釈迦様が生まれられたのは、現代ではネパールにあたります。
日本でいえば沖縄のほんの少し北のあたりです。
ですが沖縄と違って内陸なので、寒暖差が大きく、冬は寒くなります。
そして雨期もあります。
それで浄飯王は、夏期、雨期、冬期の三つの季節のための宮殿を造らせました。
夏には涼しい御殿に、雨季には雨を楽しめる御殿に、寒く雪の降る時は暖かい御殿にシッダルタ太子を住まわせていたのです。
シッダルタ太子は豪華な宮殿の中で、美しいものだけを見て、快い音だけを聞き、美味しいものだけを与えられていました。
宮殿は、老いや病や死、貧困や争いといった現実の苦しみから完全に切り離されていたのです。
そのように育てられたシッダルタ太子でしたが、成長するにつれて自分の生まれ育った環境の外の世界に強い関心を抱くようになります。
そして、東西南北の4つの城門からそれぞれ1回ずつ、4回にわたって郊外へ出かけました。
この4回の郊外への外遊でシッダルタ太子が目にしたものが、
赤裸々な人生のすがたであり、その中には人生苦の根元となる苦しみもありました。
それからシッダルタ太子の人生の軌道は、本当の幸福に向かっていくのです。
シッダルタ太子は一体何を目撃したのでしょうか。
四門出遊で見た「四つの光景」
四門出遊において、シッダルタ太子は、東門、南門、西門、北門の順に、4つの門から城郭の外へ出て、4種の重要な人々と出会います。
ちなみにこの城の門というのが、宮殿の門を指すのか、城塞都市の門を指すのかはっきりは分かりません。
当時のカピラ城は、都市全体が壁で囲まれた城塞都市だったと考えられるからです。
四門出遊はシッダルタ太子14歳の時のことと説かれていますが、
14まで宮殿から出たことがないというのは少し考えにくいので、
都市の城壁の門から、何が襲ってくるか分からない外の世界を見に行ったのでしょう。
東の門を出た時の光景
14歳になったシッダルタ太子は、ある時、父である王に
「城の外に出て、世の中の様子を見て回りたい」
と申し上げます。
そこで困った父の浄飯王は、太子が老人や病人を見ないように、
城壁周辺から老人や病人を遠ざけよと家臣たちに指示しました。
その上で多くの役人や従者を太子のお供につけます。
こうして太子は初めて、都であるカピラ城の東の門から外へ出られることになったのです。
ところがこの時、老人や病人は一人もいないように人払いしたはずだったのに、
なぜか一人の老人がヨロヨロと現れます。
その老人は、頭は白く、背中は丸く曲がり、杖にすがって弱々しく歩いています。
太子は尋ねました。
「あの人は一体、どういう人だ?」
やむなく従者は答えます。
「あれは老人でございます」
こうして太子は、東門から出て初めて病人の存在を知ったのです。
なぜ老人は一人も太子の視界に入らないようにしたはずなのに、
一人だけ老人が残っていたのかというと、
確かに従者たちは王の言いつけをしっかりと実行し、人払いしていたのですが、
「帝釈天」という仏法者を守る神が、シッダルタ太子を本当の幸福に導くため、自身の姿を変え、一人の老人となり、太子の前に現れたのです。
太子はさらに尋ねます。
「『老』とは、どういうことだ?」
従者は答えます。
「私たちは年を重ねるにつれて、体の機能は徐々に衰え、容姿も変わり、顔色も悪くなります。
胃腸の消化も悪くなり、気力も弱々しくなります。
立ったり座ったりする動作さえもつらく感じられ、人生の残された時間もわずかだと感じるようになるのです。
これらすべての変化をまとめて『老い』と呼ぶのです」
それを聞いた太子は、
「ああ、それならどうして人生が楽しめるだろうか。
月日の過ぎゆく速さは、春に芽吹いたものが秋にはたちまち枯れてしまうように、
老いの訪れは、まるで雷が落ちるかのように、一瞬のことだ。
それなのにこの肉体が、どうして頼れるというのだろうか」
老いを重く受け止めた太子は、馬車を引き返して城に戻りました。
太子は、たとえ病気にかからなくとも、確実に、そして速やかに老いがやってくることに気付いたのでした。
これは現代人の私たちもまったく同じことです。
太子は城に戻ると大変落ち込み、食事も喉を通らなくなってしまいました。
それを心配した浄飯王は、500人の美女を太子に与え、気持ちを紛らわせようとします。
しばらくして太子は、やっと少し気が晴れたのでした。
南の門を出た時の光景
太子はしばらく宮殿の中で過ごしていましたが、また外に出たくなってきました。
そこで太子は従者を連れ、馬車に乗って南の城門から外へ出ます。
今度も従者たちが先回りして老人も病人も近づけないようにしていたのですが、
またしても、なぜか体は痩せ衰え、お腹の膨らんだ病人が現れ、
門の壁に寄りかかって苦しそうに息を切らしています。
太子は従者に尋ねました。
「あの人は一体、どういう人だ?」
やむなく従者は答えます。
「あれは病人でございます」
この人も実は太子を導くために帝釈天が姿を変えた病人でした。
太子はさらに尋ねました。
「『病』とは何だ?」
従者は説明します。
「およそ病気というものは、寒さによって、発熱したり悪寒を感じたりするものです。
この人はきっと、節制せずに好きなものを飲み食いして、生活も不規則だったために、病気にかかったのでしょう」
太子は言いました。
「ああ、そんなことになったら何と苦しいことだろうか!
私は裕福で身分も高く、美味しいものを好きなだけ食べ、節制しているとは言いがたい。
私もいつかはあの人のように病に苦しむ日が来るだろう。
結局、私もあの人と何も変わらないではないか」
太子は病を自分のこととして受け止め、すぐさま馬車を引き返して城に戻ってしまいました。
シッダルタ太子は、いつか自分も病にかかると知り、大変驚いたのです。
ですがこれは、現代人の私たちもまったく同じことです。
太子は東の門を出た時と同じく、また憂鬱になり、食事をとらなくなります。
浄飯王は外出を許したことを悔やみ、そして再び500人の美女を与えて、太子を慰め楽しませました。
しばらくして、また少し気が晴れたところで、三度目の外出をします。
西の門を出た時の光景
ある時シッダルタ太子は、西の門から馬車に乗って城の外へ出られました。
従者たちは細心の注意を払って、老人も病人も、ましてや死人など決して近づかないように人払いを行い、万全の体制で臨みます。
ところが、しばらくするとまたしても、なぜか葬式の行列が太子の目に入るところを通りかかりました。
車に乗せられた死人を先頭に、男女が花や供物を持ち、しくしくすすり泣きながらついて行きます。
太子はまた従者に尋ねました。
「あれは一体、何なのだ?」
従者は答えます。
「死人でございます」
これも実は太子を導くために帝釈天が姿を変えた死人でした。
太子は問いただします。
「『死』とは、どういうことだ?」
従者は答えます。
「死とは、人生の終わりを迎えることでございます。
寿命には長短がございますが、寿命が尽きれば、息絶え、生命は肉体を離れ、残された体は朽ち果てます。
これを死と申します。
この世に生を受けたもので、死を迎えないものなど、一つとしてございません」
あまりのことに太子は大きく衝撃を受け、人生の儚さを嘆かずにはいられませんでした。
「ああ、死というものは、なんと辛く、これほどまでに心を激しく揺さぶるものなのか。
この世に生を受けた以上、必ず老い、病、そして死という苦しみからは逃れられない定めにある。
なんと苦しいことではないか」
死は自分の確実な未来と知り、大きなショックを受けた太子は、馬車を引き返して城に戻りました。
老病死という人生の真のすがたを目の当たりにし、
お金や財産、地位、名誉、家族、健康など、人生のどんな幸せも、やがて必ず崩れ去ってしまうことが知らされたのです。
このことについても、現代人の私たちも紛れもなく同じ状況にあります。
太子はまた憂鬱になり、食事をとらなくなりました。
王は太子のこのような姿を見て、ますます心配になります。
王は太子の気持ちが分からず、言いました。
「この国は、やがてそなたのものになる。
この国や国民を治めるのが、そなたの務めなのだ。
それなのに、どうして先のことをあれこれと思い悩んで、自身をそんなにも疲れさせ、苦しんでいるのか?」と。
そして再び500人の女性を太子に与え、太子を慰め楽しませようとしました。
しかし、老病死によってやがて必ず崩れてしまうという問題がある限り、
どんなに楽しいことも心から楽しむことができません。
シッダルタ太子は、苦しみ悩みの人生をどうしたらいいか分からず、一人悩むのでした。
北の門を出た時の光景
そして最後に、太子は従者を連れ北の門を出ます。
今度は、従者の頑張りが実り、病人も老人も死人も現れませんでした。
ところが、シッダルタ太子の目に入った人がいました。
粗末な衣を着て、托鉢しながら、地面を見つめ歩いています。
太子は尋ねました。
「あの人は一体、どういう人だ?」
従者は答えます。
「あれは修行者でございます」
これも実は太子のために帝釈天が現れた姿でした。
太子は言いました。
「修行者とは、どういう者のことだ?」
従者は答えます。
「聞くところによりますと、修行者とは、老いや病や死によっても崩れない本当の幸福を求めて、世俗を離れ、出家し、修行している者です」
太子は修行者の欲望に流されない凛とした姿に感じるものがあり、大変喜びます。
「素晴らしい。私が求めるべき本当の幸福になるための道かもしれない」
そう言うと、すぐさま馬車を引き返して城に戻りました。
シッダルタ太子は、修行者が目指しているところにこそ、本当の幸せがあることを感じ、人生に一筋の希望を抱きました。
こうしてシッダルタ太子は、老いと病と死の解決を目指して出家することになるのです。
出家とはどういうことかについては、以下の記事をお読みください。
➾出家とは?仏教における意味・目的と得度との違い
このようにシッダルタ太子は、四門出遊の4つの出会いから多くのことを学び、人生の重大な転機を迎えたわけです。
このシッダルタ太子の気持ちは分かりましたでしょうか?
やがて老いて、病にかかり、死んでいくことは誰でも知っていると思いますが、
それならできるだけ若くて健康な間に、
楽しめるだけ楽しめばいいのではないのでしょうか?
四門出遊の解説
シッダルタ太子は、四門出遊によって老いと病と死という人生の厳しい現実を直視し、これでは心からの安心も満足もないと思います。
それに対して、その気持ちを全く理解できなかったのが、お父さんの浄飯王です。
浄飯王とシッダルタ太子の違い
浄飯王は、シッダルタ太子に偉大な王なって欲しいと思い、最初から老い、病、死といった人生の苦しみを見せないように育てています。
三時殿という別荘を建てて、美味しいものを食べさせ、欲しいものは何でも与えます。
さらに少し落ち込めば、500人の美女をはべらせて毎日宴会を催して気を紛らわせます。
お金も地位も名誉も健康にも家族にも恵まれ、できるだけ苦しいことは減らして、誰よりも幸せな暮らしをしているシッダルタ太子が、一体何に苦しんでいるのか、浄飯王には全く分かりませんでした。
どれだけ太子が苦しみを訴えても、浄飯王は物質的に豊かで、500人の美女がいれば、シッダルタ太子の気が紛れると考えていたのです。
老病死は誰もがやってくる未来ですが、そんなことよりも今の周囲のライバルたちから国を守ることや、この生活を維持することのほうが大事でした。
どうして浄飯王とシッダルタ太子に、このような違いがあるのかというと、
浄飯王には見落としている苦しみがあるのです。
これは多くの人が見落としている苦しみです。
浄飯王は多くの人の代弁者なのです。
その多くの人が見落としている苦しみを知らせるために、
お釈迦様は、老いと病と死によって教えられているのです。
仏教の出発点は、生老病死の四苦なのです。
老いの苦しみについて
シッダルタ太子が南門の外で見たのが老人でした。
およそ人として生まれたからには、昔の人も現代人も年をとります。
そして年を重ねるにつれて、私たちは様々な苦しみに直面します。
若い頃には想像していませんが、年をとると体や心に大きな変化が現れてきます。
かつて誰もが認めるほどの美貌を誇っていた小野小町は、こんな歌を詠んでいます。
 小野小町
小野小町面影の 変わらで年の つもれかし
たとい命に 限りあるとも
(小野小町)
これは、ああ、わたくしの目も眩むばかりの美貌よ、どうか時を超えても色褪せることなく、年輪を重ねておくれ。
たとえ、この儚い命に終わりが来ようとも……、ということです。
容姿が美しければ美しいほど、年をとることが大きな苦しみにつながります。
もちろん、年齢を重ねることで深まる魅力もありますが、
やはり容姿の衰えに対する苦悩は大きいようです。
それで小野小町は、見た目が変わるより死んだ方がましとまで言っているのです。
現代では「アンチエイジング」が流行し、
少しでも老いを遅らせようと、多くの人が全力で努力しています。
しかし、どんなに頑張っても、老いは確実に、そして容赦なく私たちに近づいてきます。
肉体はまるで長年使い込んだ機械のように、様々なガタがきます。
若い頃は軽々とできていたことが、急に辛くなったり、痛みを感じるようになります。
少しの散歩や階段の上り下りさえ、息切れをしたり、足腰の痛みに悩まされます。
目は、細かい文字が見えづらくなり、読書や手芸にもやりづらさが出ます。
耳が遠くなり、家族や友人との会話も難しくなり、置いてきぼりのような寂しさを感じることさえあります。
風邪をひいただけでもなかなか治らず、免疫力は下がり、
時には肺炎などの大きな病気にもつながりかねません。
ちょっと転んだことがきっかけで寝たきりになってしまい、
トイレに行くことさえ一人ではできなくなるなど、
日常生活を送る上で大きな困難に直面することもあります。
年をとると若さの価値を実感し、ムダに過ごしてきた時間を後悔するのです。
これは、命ある限り避けられない、どんな人にも必ず来る未来です。
浄飯王も、年をとれば老いの苦しみが分かります。
ですが、シッダルタ太子は、まだ年をとっているわけではありません。
若いうちに、時間はあっという間に流れ、すぐに老いて、どんな幸せも崩れ去ってしまうことに気づいたのです。
すぐれた人ほど先のことを考えているといわれますが、
シッダルタ太子は目の前のことだけ考えるのではなく、
人生を長期的に俯瞰して、先のことまで考えているところがまず違います。
ですが、これは先のほうまで考えられるという能力的な違いだけではありません。
病の苦しみについて
人間の体は、「病の器」と言われるように、私たちはいつか必ず何らかの病気にかかるものです。
たとえ食生活に気を配り、運動を習慣にし、十分な睡眠時間を確保していたとしても、年をとって体が弱れば病気になることは避けられません。
風邪を引いている時は、食欲が落ちて何も食べられません。
たとえ食べたとしても、どんな美味しい料理も味がしなくなります。
楽しみにしていたカラオケや飲み会も、体の怠さで全く楽しめません。
アトピーのような慢性的な病気であれば、命に関わることはなくても、かゆみに悩まされ、ストレスの多い毎日を送ることになります。
さらに、命に関わるような大きな病気にかかってしまえば、
激しい痛みだけでなく、学校や仕事にも行けなくなり、
将来への不安や社会から孤立したような寂しさに打ちひしがれるでしょう。
病気の研究が進み、多くの病気が治るようになったり、症状が落ち着くようになったとはいえ、いまだに治らない病気も多く、新たな病気も増え続けています。
もし治らない病気にかかってしまった時、
「自分は真面目に生きてきて、悪いことなんてしていないのに、なぜこんな目に遭わなければならないのか」
と、自分の人生を恨んだり、運命の不条理を嘆いたりすることもあるかもしれません。
アメリカの思想家であり哲学者でもあるラルフ・ウォルドー・エマソンは、
こんな言葉を残しています。
 ラルフ・W・エマソン
ラルフ・W・エマソン健康は第一の富である。
(ラルフ・ウォルドー・エマソン)
どんなに多くの財産や地位を持っていても、
それは健康という土台の上に成り立っているのです。
日本の作家、武者小路実篤は、著書『人生論』の中でこう述べています。
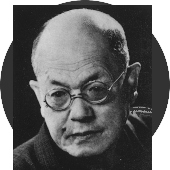 武者小路実篤
武者小路実篤人生にとって健康は目的ではない。
しかし最初の条件なのである。
健康の価値は病気してはじめてわかる。
しかし健康になってしまえば、もう健康のことを忘れる。
忘れるところがおもしろいところだ。
(武者小路実篤『人生論』)
これは、人生における幸福にとって、健康そのものが幸福ではないけれども、健康でなければ幸せになることはできない、という意味です。
さらに、健康を失って初めてその大切さに気づくという、人間の認識の甘さも指摘しています。
浄飯王も、病気になれば苦しいのは分かります。
現代日本よりも衛生状態は悪く、予防接種もないので、今まで病気になったことも、一度や二度ではないでしょう。
ですが、病気が治れば健康の有り難さを忘れてしまう普通の人です。
一方、シッダルタ太子は、これまで病気らしい病気もしたことがなく、若くて健康です。
ところが、病人を目撃し、それについて聞いただけで、どんなに肉体を大事にしていても、必ずいつか健康が失われ、病によって多くの幸せが崩れ去ってしまうことに気づきます。
シッダルタ太子は、病気になれば病気の苦しみももちろん分かりますが、
悩んでいるのは病気の苦しみ自体というよりも、
やがて必ず病気になることによって、健康をはじめとする幸せが続かないという
「無常」を嘆いているのです。
これが、能力の優劣に関係なく、多くの人がなかなか気がつかない苦しみです。
死の苦しみについて
人生で耐えがたい苦しみがやってきた時、私たちは「死ぬほど苦しい」と表現します。
それは、死が人生最大の苦しみだからです。
私たちの「死」とは、単に肉体が終わるという単純なものではありません。
それは、この地球上のあらゆる美しいもの、愛する家族、友人、そして最も大切に思っていた人々との、避けられない別れでもあります。
今まで大切にしてきた幸せが総崩れになり、独り寂しくこの世を去らなければならないのです。
そして、何よりも大切にしてきた自分の肉体とも、別れなければなりません。
腕や指が一本失われただけでも苦しいのに、
ましてや肉体そのものと完全に別れるということは、
想像を絶するほどの苦しみです。
死の苦しみは、肉体的な苦痛ももちろんありますが、
仏教では、人が臨終を迎える際には「後悔」と「恐れ」が押し寄せてくると説かれています。
大命まさに終らんとして、悔懼こもごも至る。
(漢文:大命将終悔懼交至)(引用:『大無量寿経』)
ここで「大命まさに終らんとして」とは、命がまさに終わろうとする時に、ということです。
それは、この世との別れであり、未知の次の世界へ旅立つ入り口に立つ時です。
「悔懼こもごも至る」とは、「過去への後悔」と「未来への恐れ」が、交互に心に押し寄せるということです。
「過去への後悔」とは、私たちが人生という舞台で追い求めてきたものが、本当の生きる意味ではなかったという思いです。
死という一方通行の旅路においては、この世で必死に集めたお金も、大切に守ってきた財産も、一円たりとも持っていくことはできません。
舞台を降りるまさにその時に、 本当に求めるべきものが間違っていたという後悔で、苦しむのです。
「未来への恐れ」というのは、これからどうなるか全く分からない未来への、心の底からの不安です。
「死んだらどうなるんだろう?」という、はっきりしない将来への恐怖です。
これは、現代ではスピリチュアルペインといわれています。
臨終にいたって、人生の意味が分からない苦しみに気づくのです。
臨終に、自分の人生に意味があったと思えず、まもなく旅立つ先も分からずに苦しむのです。
この苦しみは、医学では取り除くことができません。
死の問題がある限り、一切の幸せが最後、崩れてしまうのです。
修行者との出会い
浄飯王は、この苦しみが分からなかったのですが、
死人を見た時の太子の気持ちは、飛行機にたとえると分かりやすくなります。
あなたは空と海しか見えない広い海の上を飛行機で飛んでいるとします。
凄いスピードで飛んでいるのですが、目的地の飛行場がどこにあるのかは分かりません。
ですが、燃料には限りがあります。
どれくらい燃料が残っているか分からないので、いつ燃料が切れるか分かりません。
そんな飛行機の中で、
「燃料が限られているのはもちろん知ってるけど、一番美味しい機内食を食べて、一番面白い機内映画を観ればいいじゃないか。
一体何が不満なんだ」
と思っているのが浄飯王です。
それに対して、
「やがて墜落することが決まっていて、
しかもいつ墜落するか分からない飛行機の中で、
機内食や機内映画を楽しむどころではない」
と思ったのがシッダルタ太子です。
飛行機はまだ墜落してはいないのですが、確実に墜落します。
普通は機内騒然としてみんな真っ青になるはずです。
それなのに、みんなわいわい空の旅を楽しんでいるように見えるので、
「どうしてそんな食べたり飲んだりして楽しめるんだろうか。
みんなこの状況が分かっているんだろうか」
とシッダルタ太子はその状況の打開策に悩んでいたのです。
四門出遊の最後に、シッダルタ太子が北門の外で見たのが修行者でした。
太子は、美味しい物を食べたり、財産を貯めるような世俗的な欲望を離れ、何かに取り組んでいる様子に触れて、
自分は老いや病、死という問題を克服し、本当の幸せを求めなければならないと直感したのでした。
太子は「老病死の苦しみ」を乗り越える方向に唯一の希望を見出したのです。
四門出遊が教える2つの苦しみ
仏教では、2つの苦しみが教えられています。
1つ目は生活苦、2つ目は人生苦です。
1つ目の生活苦というのは、
お金がなくて買いたい物が買えずに苦しいとか、病気になって苦しいとか、
職場の人間関係がうまくいかずに苦しいというような、生きていく上での苦しみです。
人生でいえば、どう生きるかという生きる手段の苦しみともいえます。
これは誰でも分かります。
2つ目の人生苦は、「必ず死んでいくのに生きる意味はあるのか」という
生きる目的が分からない苦しみです。
これは人生全体を俯瞰した時に、なんのために生まれてきたのか分からない苦しみともいえます。
飛行機でいえば、水平線しか見えない広い海の上で、目的地の飛行場がどこにあるのか分からない苦しみです。
たとえ機内食が美味しくて、機内映画が楽しかったとしても、空の旅は楽しめません。
生活苦は、どんな人でも気づく分かりやすい苦しみですが、
この人生苦に気づく人はわずかです。
ですが、どんなにお金があって、やりたいことをやっても、
何となく空虚で虚しい心となって現れます。
四門出遊が教えているのは、老苦や病苦、死苦でもありますが、
単にそれだけではありません。
分かりやすい老苦や病苦、死苦を教えることによって、
やがて必ず老いて、病にかかり、死んでいかなければならないことを教え、
何のために生きているのか分からない、
人生苦を知らせようとしているのです。
仏教が解決するのは、生活苦ではなく、人生苦です。
生活苦はどこまでいってもなくなりませんが、人生苦は完全になくして、
人間に生まれてよかったという喜びの身になれます。
シッダルタ太子は、この人生苦に悩み、29歳の時に出家します。
そして6年間の想像を絶する厳しい修行の末、
ついに大宇宙最高の仏のさとりを開き、
老いと病と死を超えた本当の幸せを体得します。
そして、老病死を超えた本当の幸せと、
本当の生きる意味を生涯説かれたのが仏教です。
では、その老病死を超えた本当の幸せには、どのようにしたらなれるのでしょうか。
それには、釈迦が明らかにされた死の問題を引き起こす、苦しみの根本原因を知らなければなりません。
その苦しみの根本原因については仏教の真髄ですので、
メール講座と電子書籍にまとめてあります。
ぜひ一度、見ておいてください。
関連記事
この記事を書いた人

長南瑞生(日本仏教学院創設者・学院長)
東京大学教養学部で量子統計力学を学び、1999年に卒業後、学士入学して東大文学部インド哲学仏教学研究室に学ぶ。
25年間にわたる仏教教育実践を通じて現代人に分かりやすい仏教伝道方法を確立。2011年に日本仏教学院を創設し、仏教史上初のインターネット通信講座システムを開発。4,000人以上の受講者を指導。2015年、日本仏教アソシエーション株式会社を設立し、代表取締役に就任。2025年には南伝大蔵経無料公開プロジェクト主導。従来不可能だった技術革新を仏教界に導入したデジタル仏教教育のパイオニア。プロフィールの詳細・お問い合わせ
X(ツイッター)(@M_Osanami)、ユーチューブ(長南瑞生公式チャンネル)で情報発信中。メールマガジンはこちらから講読可能。
著作
- 生きる意味109:5万部のベストセラー
- 不安が消えるたったひとつの方法(KADOKAWA出版)
京都大学名誉教授・高知大学名誉教授の著作で引用、曹洞宗僧侶の著作でも言及。




