死苦とは?
「死苦」とは、死ぬ苦しみです。
お釈迦様は、人生で避けることのできない四苦八苦の1つに教えられています。
不老不死は誰もが願うことですが、「生ある者は必ず死に帰す」といわれるように、
どんな人も死は免れません。
では、死苦はどのように克服すればいいのでしょうか?
死苦の意味
「死苦」とは、死ぬ苦しみです。
「死苦」について辞典を見てみると、このような意味が出てきます。
仏語。
四苦の一つ。
衆生が免れることのできない死という苦しみ。
また、死ぬときの苦しみ、あるいは、死によって生ずるさまざまな苦しみ。(引用:小学館『スーパーニッポニカ 国語辞典』)
仏教で教えられる意味と、ほとんど変わりません。
四苦とは何かというと、仏教では、人生で避けることのできない苦しみを8つに分けて
四苦八苦と教えられています。
四苦とは、生苦、老苦、病苦、そして今回の「死苦」の4つの苦しみです。
八苦とは、四苦に愛別離苦、怨憎会苦、求不得苦、五陰盛苦の4つを加えたものです。
この後半の4つは生きる苦しみですが、四苦八苦の中でも、4番目の「死苦」が最も苦しく、根本的に重要です。
『正法念経』にはこう説かれています。
人、死するの時、大苦悩を受く。喩うべき法なし。
一切の世人、皆まさに死あるべきこと決定して疑いなし。
(漢文:人死之時受大苦悩 無法可喩 一切世人皆当有死決定無疑)(引用:『正法念経』)
これは、人は死ぬ時、大きな苦悩を受ける。それは何物にもたとえられない。
すべての人はみな、将来必ず死ぬことは疑いなく決定している、ということです。
「死ぬほど辛い」という言葉があるように、死ぬほど苦しいことはないのです。
このような死ぬ時受ける大苦悩が「死苦」ですが、
このお経にも説かれているように、死にはある性質があります。
死の2つの性質
どんな人の死にも、共通して2つの性質があります。
どちらも非常に困った性質です。
1つは100%確実にやってくるということ、
もう1つは、いつ来るか分からない、ということです。
1:100%確実
まず、死はすべての人にとって、100%確実な未来です。
私たちは生まれた時から、1日また1日と死に近づいていきます。
これを禅僧の一休は、こう言っています。
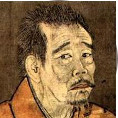 一休
一休門松は 冥土の旅の 一里塚
(一休)
この人生はすべて、冥土への旅だということです。
これは否定しようがありません。
冥土というのは、これは死後の世界です。
「冥土の旅の一里塚」ということは、近づいているということです。
私たちは、おぎゃっと生まれたその時から、
1日経てば1日経つだけ冥土に近づいています。
一夜明ければ一夜明けるだけ冥土に近づいています。
どれだけアンチエイジングに努めても、
病気知らずの健康体だと言っても、
死から逃れられる人はありません。
どんなに地位の高い人でも、どれだけお金があっても、
生まれたからには必ず死んでいかなければなりません。
絶対に死にたくないのに、絶対に死んでいかなければならないということは、
それだけ苦しいということです。
このことを、『阿含経』の教えをまとめた『大毘婆沙論』には
こう解説されています。
死、よく可愛の寿命を断滅するが故に死苦と名づく。
(漢文:死能断滅可愛寿命故名死苦)(引用:『大毘婆沙論』)
「可愛」とは、好ましいとか、愛すべきということです。
死は、絶対に失いたくない命を断ち切ってしまうので、苦しみといわれる、ということです。
死にたくないのに絶対に死ななければならないので、苦しみなのです。
2:いつ来るか分からない
しかも死はいつ来るか分かりません。
死というと、みんな30年も50年も先のことのように考えて、
まだまだ遠い先のことだとのんきに構えています。
ですが、寿命が決まっているわけではないので、
平均寿命までは生きられるという保証はありません。
交通事故で毎日たくさんの人が亡くなっています。
その中には、自分より若い人もたくさん含まれています。
その人たちが、朝顔を洗う時に、「今日が自分の死ぬ日だ」と悲壮な覚悟で鏡を見たかというと、そうではありません。
普段と同じように眠そうな顔をして、まさか自分が今日死ななければならないなんて少しも考えていなかったはずです。
そんな、自分が死ぬとは思っていない人が死ぬのです。
年を重ねた高齢の人が先に亡くなって、
若い人が後に亡くなると決まっているわけではなく、
死は、いつ自分の身にやって来るか分からないのです。
仏教では、これを「老少不定」といいます。
「老」とは年をとった人、
「少」とは若い人、
「不定」とは決まっていないということで、
年をとった人が先に死んで、若い人が後から死ぬとは決まっていない。
無常の前には、みな同い年ということです。
死ぬのは1年後かもしれませんし、
1ヶ月後かもしれません。
明日かもしれませんし、1時間後かもしれません。
この一瞬後に命を失わないとも限らないのです。
ですが、たとえそうであっても、自分は死は怖くない、という人もいるのではないでしょうか。
死は怖くないから死苦もない?
「自分は死は怖くない」という人は、よくいます。
確かに昔は怖かったけど、死に対する考え方を変えたので、
最近ではもう怖くなくなった。
私は死については何の問題もない、というような人です。
そういう「死は怖くない」という人を分類すると、大体次の3通りになります。
1つ目は、老衰で安らかに死ねば、死は苦しくないという人、
2つ目は、天国のような楽しい場所、素敵な所へ行けると思っているから、
3つ目は、自分の死ということが漠然とし過ぎていて、全く実感がないからです。
老衰で安らかに死ねば死は苦しくない?
たまに、自分のばあちゃんは、安らかににっこり笑って死んでいった、という人がいます。
それは、苦しくなかったのでしょうか?
年を重ねると、身体の色々な部位に支障が起きてきます。
耳が遠くなったり、目が見えにくくなってきたり、
足腰が弱くなったりといった具合です。
それはそれだけで老苦という苦しみなのですが、
それについては以下の記事をご覧ください。
➾老苦の意味と老いの苦しみを解決する唯一の方法
そうやって、特に病気というわけでもなく、身体の器官が老化し
衰弱して亡くなっていくのを、世間で老衰死とか、単に老衰ともいわれます。
自然死ともいわれます。
よく老衰で亡くなった方のことを、
「眠るように死んでいった」とか、
「穏やかな死に様だった」といわれますが、
老衰の場合、本当に苦しみはないのでしょうか。
確かに病気の時のような、患部が痛いとか、病気による諸症状は
あまりないかもしれません。
ですが、身体の色々な器官の働きが衰えていくのに
苦しみを感じないということはありません。
歯が抜けたり消化器官が衰えることによって、
美味しく食事をすることができなくなってしまいます。
認識力の低下により、周りで起きる様々な出来事がハッキリと認識できなくなり、
心にぼんやりと映るようになります。
呼吸器官の衰えによって、息をするのも不安定で大変な状態になります。
自然死は、そのようにだんだんと死に向かっていくこと自体が苦しみです。
周りの元気な人が、眠りにつくようだとか、穏やかだと言っているだけで、
本人は単にしゃべることができずに「苦しい」と言えないだけです。
しかも後で出てきますが、死の苦しみの本質は肉体的なものではなく、
精神的なものです。
死んだら天国へ行ける?
死は怖くないという人の2つ目に、
「天国のような楽しい場所へ行けるから」というものがあります。
他にも、先に死んだ愛する家族のもとへ行けるとか、
死んだら天国へ行けるとか、極楽へ往けるという人もいます。
もし本当に、死んだらそんな幸せな場所へ行けるのであれば、
人生は四苦八苦が充満する苦しいところなので、
早く死んで行ったらいいのではないでしょうか?
環境を破壊し、他の生き物を殺して食べてまで、苦しみながら生きるのは
本人にとっても周りにとってもよくありません。
それでも早く死なないのはなぜかというと、
死ねば確実にそこへ行けるかどうか、
本当はハッキリしないからです。
死んだらどうなるか分からないから、死ぬのが怖いのです。
私たちが「死ぬのが怖い」と思うのは、
死んだ後の行き先がハッキリせず、不安だからです。
死ぬのが怖いから、口では死んだら楽しい所へ行けると言っていても、
少しも早く行こうとしないのです。
自分が死ぬとは思えない
死は怖くないという人の3つ目は
「自分が死ぬとは思えない」という人です。
これはよくあることで、
ほとんどの人にとって、自分が死ぬという実感がわきません。
自分の死ということと正面から向き合わない限り、自分が死ぬとは思えません。
死についての敏感さを、お釈迦様は『雑阿含経』に
4通りの馬にたとえて教えられています。
- 鞭影を見て驚く馬
- 鞭、毛に触れて驚く馬
- 鞭、肉に当たって驚く馬
- 鞭、骨にこたえて驚く馬
「鞭」とは、無常であり、死のことです。
鞭影を見て驚く馬とは,
鞭をふりあげた影を見て、走り出す馬です。
これはすぐれた駿馬です。
どんな人をたとえられたのかというと、
桜の花が散るのを見て、
「自分もやがて、あのように散る時が来るんだな、
死んだらどうなるんだろう」
と驚く敏感な人です。
次の鞭、毛に触れて驚く馬は、
鞭の影を見ただけでは走り出さないのですが、
鞭が少し毛に触れて、走り出す馬です。
これも駿馬です。
どんな人かというと、セレモニーホールの横を通った時に、
誰かの葬式が執り行われていて、次々と人が入っていくのを見て、
「あの白と黒の看板に、自分の名前が書かれる時が来るんだな」
と驚きが立つ人です。
また、ニュースで有名人が死んだと聞いて、自分もやがて死ぬ時が来ると驚く人です。
3番目の鞭、肉に当たって驚く馬は、
鞭が肉に当たって驚く馬です。
これは普通の馬です。
親戚や知人の葬式に参加して、
「自分もこうなる時が来るんだな」
と驚きが立つ人です。
また、目の前で交通事故が起きて、人が死んだのを見て、
「自分もやがて死ぬんだな」
と驚く人です。
最後の鞭、骨にこたえて驚く馬は、
2回や3回鞭で打たれても走り出さないのですが、
肉が切られて鞭が骨に当たってようやく走り出す駄馬です。
友達が死んでも、近所の人が死んでも驚きが立たず、
家族が死んでようやく
「自分もこのように死んでいかなければならないのか」
と驚く人です。
このように、死に対して敏感な人から鈍感な人まで、色々いると教えられています。
ですが実際は、親を棺桶に入れても、
夫を棺桶に入れても
妻を棺桶に入れても
子供を棺桶に入れても驚かない人がたくさんいます。
それだけ死に鈍感で、自分が死ぬとは思えないということです。
自分が死ぬと思えなければ、死が怖いはずがありません。
死を自分のこととして受け止められていないだけです。
「死は怖くない」「死は苦しくない」といって自分の死から目を背けている人に、
お釈迦様はこのように例えで教えられています。
死は、ちょうど危険極まりない山道で食べ物もない。
人里遠く離れて連れはなく、昼夜休まず歩き続けても、果てしがない。
山奥深く昼間でも暗い森の中を明かりもなく、うろうろしているようなものだ。
そして死は、別に入口もないけれども、自由に入ることができる。
また死は、常に私たちの身辺に付きまとっているものだが、それと知ることもできない。
迦葉よ、これらのたとえを考えてよく知るがよい、死は真に大きな苦しみであることを。
一応、出典の『涅槃経』のお言葉を挙げておくと、以下の通りです。
死は険難処において資糧あることなし。
去処懸遠にして伴侶なく、昼夜常に行いて辺際を知らず。
深邃幽闇にして灯明あることなく、入るに門戸なくしてしかも処する所有り。
(中略)
身辺に敷在すれども、覚知すべからず。
迦葉、これらの喩及び余の無量無辺の譬喩を以て、まさに知るべし、これ死は真に大苦たるを。
(漢文:夫死者於険難処無有資糧 去処懸遠而無伴侶 昼夜常行不知辺際 深邃幽闇無有灯明 入無門戸而有処所(中略)敷在身辺不可覚知 迦葉 以是等喩及余無量無辺譬喩 当知是死真為大苦)(引用:『大般涅槃経』)
死は決して逃れることができない上に、いつ自分にやって来るか分からず、
常に死と隣り合わせの極限状態にあることから、それが不安と怖れを生じさせる、
そういったことで死苦は大きな苦しみなのだと教えられているのです。
無自覚に死を恐れる心
「死」の恐怖は、あまりにもの凄いために、普段は感じなくなっています。
死は直視できない
死はあまりにも恐ろしいために、メーターが振り切れて見ないようにしているのですが、
少し薄めるとみんな怖がり始めます。
例えば、死の恐怖を感じないという人でも、
スーパーに売っている野菜に、
放射性物質のヨウ素135とか、セシウム137がついていたりすると、
買いません。
原子力発電所の近辺でとれた大安売りの野菜があれば、
死が怖くないなら買えばいいのに、誰も買わないのではないでしょうか。
また、発がん性物質なども、かなり気をつけます。
添加物を使って安く美味しくなったり、保存料で食中毒が防がれているのですが、
よく表示を見て危険な添加物を避けようとします。
それはガンになると死ぬからです。
ガンは自覚症状がないので、
苦しみは風邪のほうが大きいのに、
「風邪になるのと、ガンになるのと
どっちを選びますか?」
となったら風邪だと思います。
それは、ガンだと死ぬ可能性が高いからです。
ガンになっても100%死ぬわけではなく、
最近は早期治療で回復する人もありますので、
死ぬ確率が高いだけです。
それでもみんな恐れるのは、死が怖いからです。
フランスの文学者、ラ・ロシュフコーは、こう言っています。
 ラ・ロシュフコー
ラ・ロシュフコー太陽と死とはいずれもじっと見つめることができない。
(ラ・ロシュフコー『格言集』)
死は恐すぎて考えられないのです。
長生きしたい心は死を先延ばしにしたい心
それでも、それは死が怖いのではなくて、
ただ長生きしたいだけだという人もあるかもしれません。
現代はどんどん平均寿命が延びて、人生100年時代といわれ、
80歳代や90歳代の人も多くあります。
そういう方を見ていると、自分もそのくらいの年齢までは生きていられるように思ったり、できればそのくらいまで長生きしたいと思うものです。
この「まだ死なない」とか「長生きしたい」という心は
自分の死を遠い先に追いやっている心です。
ですが、死ななくなったわけではないので、
いよいよ自分が死ぬという時が必ず来ます。
死に直面した人の感想
いよいよ死に直面すると、それまで死は怖くないと思っていた人も豹変します。
冬山で遭難した大学生の遺書
例えば、ある京都の大学の山岳部で、12月30日に冬山に登った大学生が遭難しました。
1月1日午前1時、雪が迫り、思うように動けない広さのテントの中で、
空腹と孤独に耐えながらこう書き残しています。
「お母さんへ。
山の死を美しいとするのは一種の感傷でした。
生還すればもう山をやめて心配はかけません」
「再び母へ。
ありきたりのことだが先に行くのを許して下さい。
お父さん、心配かけて申し訳ありません」
その大学生は山岳部の部長だったので、冬山を登頂できる自信があったのでしょう。
そして手記からは、普段、「山の死を美しい」と言っていたことが分かります。
お父さん、お母さんにお詫びしていることから、冬山に登ることを両親が心配して反対したのでしょう。
それを「冬山で死ぬのは美しい、やりたいことをやって死ねれば本望だ」と言って、押し切って出てきたのかもしれません。
そして遭難し、いよいよ死に直面すると、もう山をやめると
人生観が180度変わっています。
死は美しいのではなく、恐ろしく、苦しいものなのです。
残念ながら、3ヶ月後、雪解けの4月に遺体となって発見されました。
十返舎一九の辞世
江戸時代後期の戯作者、十返舎一九は辞世に
「今日までは 人の事だと 思いしに
俺が死ぬとは こいつたまらん」
と遺しています。
死というと、とても自分のこととは思えず、他人事だと思っていたのに、
いざ自分にやって来ると、たまらない感じがすることを謳っています。
諸行無常なのだから自分も死んでいくという事実を受け入れ、
それに向けて準備できる人は多くないということです。
そのため、自分の死が目前に迫ってきた時、大きな苦しみを受けることになるのです。
ナポレオンの最後
19世紀のフランスの皇帝ナポレオンは、数々の功績をおさめて英雄と呼ばれ、地位も名誉も手に入れた人です。
ところが、60万人の大軍でロシアに遠征して30万人以上の犠牲者を出し、撤退を余儀なくされました。
その後、失脚してセントヘレナ島に幽閉されます。
たくさんの若者を死へ追いやったナポレオンでしたが、
そんな彼も最後は病気になります。
その病状が悪化した時、ようやく自分の死が現実のものとなって、
儚い人生を悔やみ、死の準備として祭壇を設け、死後の幸せを祈り始めました。
そんなナポレオンを見た侍医が、英雄とは思えない様子を笑った時、
ナポレオンは怒ってこんなことを言っています。
 ナポレオン
ナポレオンお前は薬を与えればいいかもしれないが、
私は霊魂の不滅を信じているのだ。
お前たちの知るところではない。
(ナポレオン・ボナパルト)
多くの人を簡単に死なせたナポレオンも、いよいよ自分が死ぬとなると気が気でなくなって、祈らずにはいられなくなったのです。
他にも、あれほど他人には「死の受容」を説いていたキューブラー=ロスも、
いよいよ自分が死に直面すると、とても受容することができず、
日本人のインタビューに対して、本心を吐露しています。
詳しくはこちらをご覧ください。
➾キューブラー・ロス『死ぬ瞬間』死の受容モデルと仏教の臨終の3段階
自分の臨終の壮絶な嵐の前には、元気な時に想像していた死の受容や、心の持ちようなど、吹き飛ばされてしまうのです。
死の苦しみとは
では、死の苦しみについて、仏教ではどのように教えられているのでしょうか。
三愛
臨終に起きてくる苦しみを三愛といわれています。
「愛」というと美しいもののように聞こえますが、
仏教では愛着とか執着という意味です。
その執着心に3つあるので、三愛といわれます。
境界愛、自体愛、当生愛の3つです。
1つ目の境界愛とは、今まで苦労して手に入れてきた、
お金や財産、地位、名誉、妻や夫、子供に対する執着です。
今まで人生の時間を使って求めてきたのですから、
いわば人生と引き換えに手に入れたものです。
元気な時は、その一部である財布を落としてさえ大騒ぎするのではないでしょうか。
それが、死ぬ時には財布どころか、家も土地も貯金も証券も全部失います。
もう二度と取り返しはつきません。
せっかく苦労して手に入ったものが、全部自分から離れていく苦しみです。
2つ目の自体愛とは、自分の体を失う苦しみです。
これまで体が資本、健康第一といって一番大事にしてきたのが自分の体でした。
自分の肉体に対する執着心は、お金や財産、地位、名誉を上回る強さです。
その最優先して守ってきた体も、いよいよもうすぐ焼かれて灰になります。
あるいは火葬場から立ち上る一条の煙になってしまいます。
肉体を失う苦しみです。
3つ目の当生愛とは、死後、生じるところに対する執着心です。
お金も失い、肉体も失い、死んだらどこへ行くのでしょうか。
いい所へ行ける保証は全くありません。
仏教では、死ぬまでの行いによって、因果の道理に従って死後が決まります。
これまであまりいいことをやってきた自覚はないのですが、
苦しい所へは行きたくない、いい所へ行きたいという不安に苦しみます。
三愛を表にまとめると、こうなります。
- 境界愛:臨終にその愛する妻子、家財等におこす執着
- 自体愛:自分の身体に対する強い執着
- 当生愛:死ぬ時に未来に生まれる所についておこす愛着心
このように、死の苦しみというのは、痛いとか、息が苦しいという肉体的なものではありません。
執着というのは煩悩だから、全部心の苦しみです。
もちろん肉体的な苦しみも色々ありますが、
死の苦しみの本質は精神的な苦しみなのです。
おまけに、三愛が起きると、仏教を学んで、死ぬまで1日何万回も念仏を称えて極楽へ往こうとしていた人も、その方法で極楽へ往く条件である正念を失うので、もうどんなに念仏を称えても極楽へは往けません。
浄土宗の祖・法然上人は、こう言われています。
三種の愛心おこり候いぬれば魔縁たよりをえて、正念を失い候なり。
(引用:『拾遺語灯録』)
「三種の愛」というのが三愛です。
三愛が起きると、一生涯、善根功徳を積んだとしても、
それはご破算になり、正念往生も不可能になります。
あの平安時代の摂関政治の頂点に立ち、栄耀栄華を極めた藤原道長も、
「この世をば わが世とぞ思う 望月の
かけたることも なしと思へば」
と詠んだ翌年には、糖尿病から視力障害を併発し始めます。
急速に体調が悪化する中、死んだらどうなるかという不安におののき、
九体の阿弥陀如来の手から五色の糸を自分の手に結んで往生を願いましたが、
いよいよ死んでいく時には、『栄花物語』に
「いみじき智者も死ぬるおりは三つの愛をこそ起すなれ」
とあるように、三愛が起きてしまいます。
死んだら極楽へ往きたいと臨終にじたばたしても無理なのです。
臨終の心のすがた
さらに、いざ自分の死に直面した時、どんな心が起きてくるかということが
『大無量寿経』というお経にこう説かれています。
大命まさに終らんとして、悔懼こもごも至る。
(漢文:大命将終悔懼交至)(引用:『大無量寿経』)
「大命」とは肉体の命ということです。
ですので「大命まさに終らんとして」とは、死に直面して、ということです。
「悔」とは、自分の過去にやってきたことに対する後悔です。
今まで一体自分は何をやってきたんだろう、
人生の最後に何が残ったか、一体何のための人生だったのかと、
それまで頑張ってきたこと、必死になって集めてきた色々のものが
何の価値もないように感じられて、
死を目前にしても崩れないような、もっと意味のあることに時間を使えばよかった、
もっと意味のあることを成し遂げなければならなかったと後悔するということです。
これを現代では「スピリチュアルペイン」といわれています。
スピリチュアル・ペインについては、詳しくは以下の記事をご覧ください。
➾スピリチュアルペインのアセスメント・ケア・治療法
「懼」とは未来への恐れです。
これから自分はどうなってしまうんだろうと、行き先が真っ暗なことに驚き、恐れる心が起きてくるということです。
臨終になって、この後悔と恐れが代わる代わる起きてくる、
これが、すべての人の臨終の心のすがただと教えられています。
では、死苦の苦しみはどうすることもできないのでしょうか。
死苦を克服する方法
このような「死苦」は、どうすれば克服できるのでしょうか。
死はどんな人も避けられないので、死苦を完全になくすことはできません。
ですが、死苦のあるがままで、死によっても崩れない真の幸福になることができます。
それは生きている今、なれます。
それには、苦しみ悩みの根本原因を知って、それを断ち切ればいい
と仏教に教えられています。
では、苦しみ悩みの根本原因とは何か、
どうすれば断ち切れるのかについては仏教の真髄ですので、
以下のメール講座と電子書籍にまとめておきました。
無料ですので、今すぐ見ておいてください。
関連記事
この記事を書いた人

長南瑞生
日本仏教学院 学院長
東京大学教養学部で量子統計力学を学び、卒業後、学士入学して東大文学部インド哲学仏教学研究室に学ぶ。
仏教を学ぶほど、その底知れない深さと、本当の仏教の教えが一般に知られていないことに驚き、何とか1人でも多くの人に本物を知って頂こうと、失敗ばかり10年。たまたまインターネットの技術を導入して爆発的に伝えられるようになり、日本仏教学院を設立。科学的な知見をふまえ、執筆や講演を通して、伝統的な本物の仏教を分かりやすく伝えようと今も奮戦している。
仏教界では先駆的にインターネットに進出し、通信講座受講者4千人、メルマガ読者5万人。X(ツイッター)(@M_Osanami)、ユーチューブ(長南瑞生公式チャンネル)で情報発信中。メールマガジンはこちらから講読可能。
著作
- 生きる意味109:5万部のベストセラー
- 不安が消えるたったひとつの方法(KADOKAWA出版)



